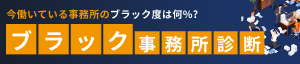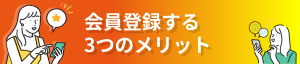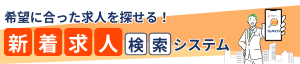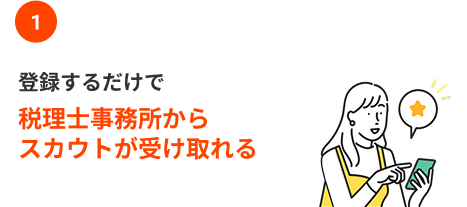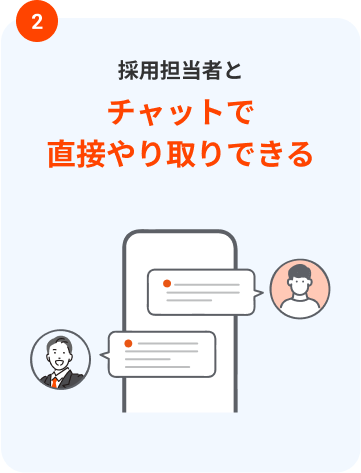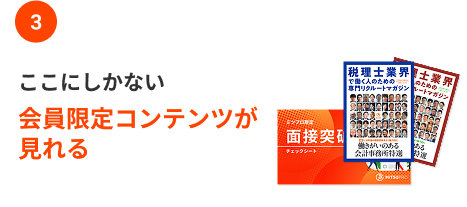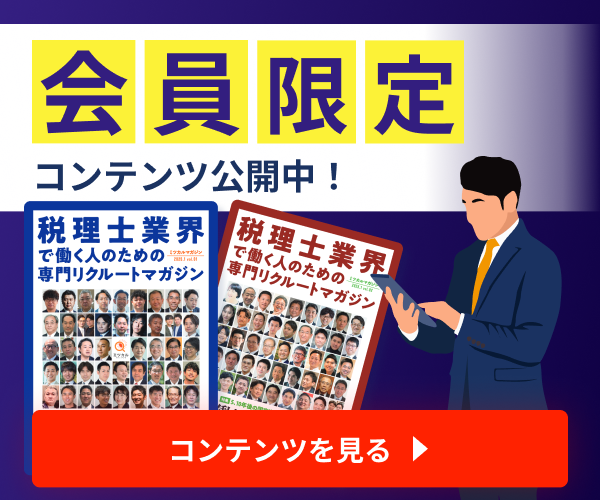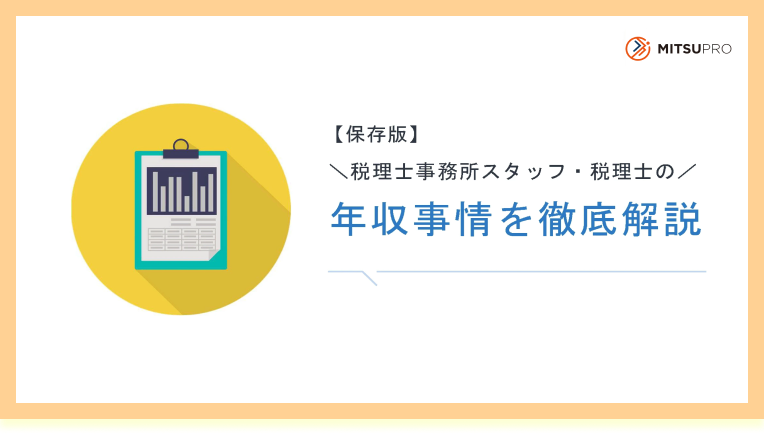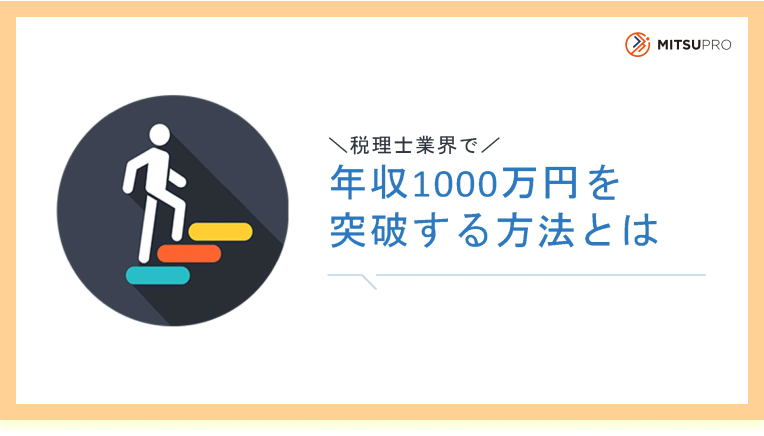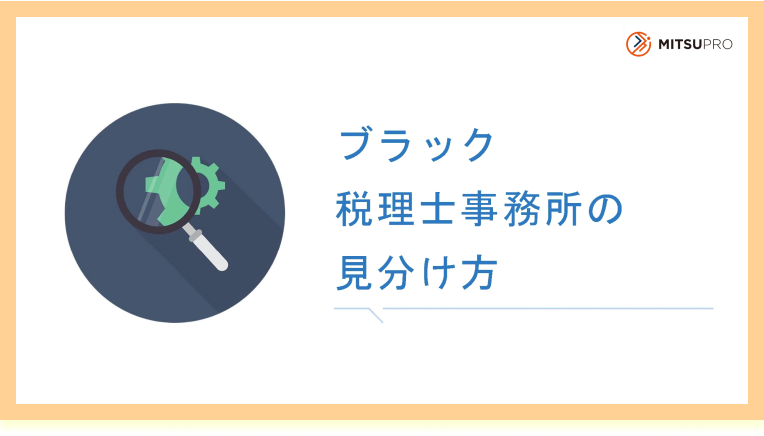INDEX
おすすめ記事
-
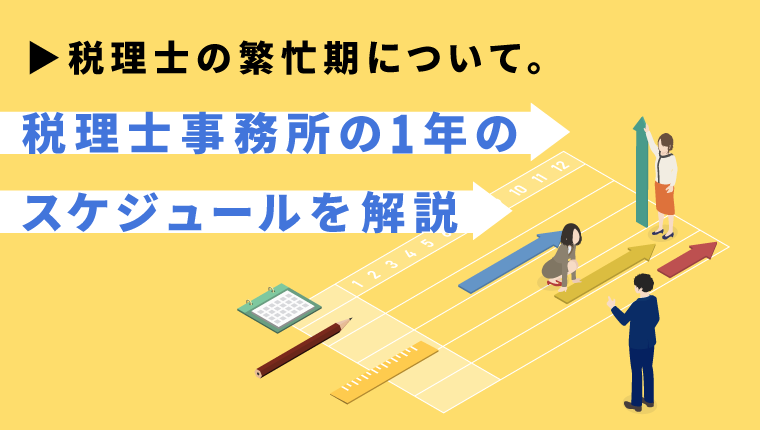
税理士の繁忙期について。税理士事務所の1年のスケジュールを解説
-
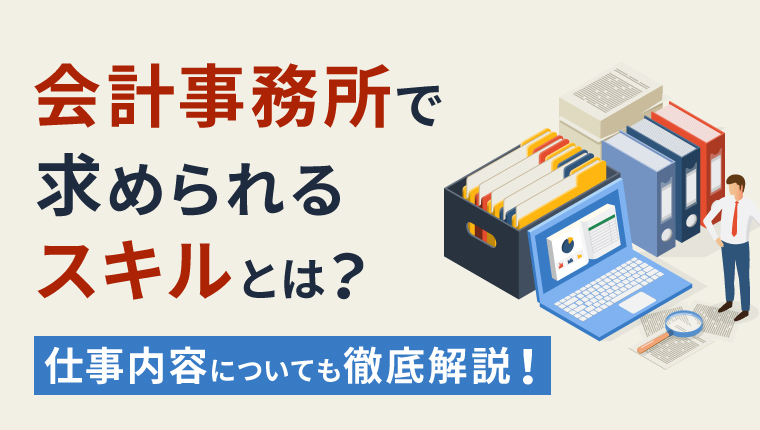
会計事務所で求められるスキルとは?仕事内容についても徹底解説!
-
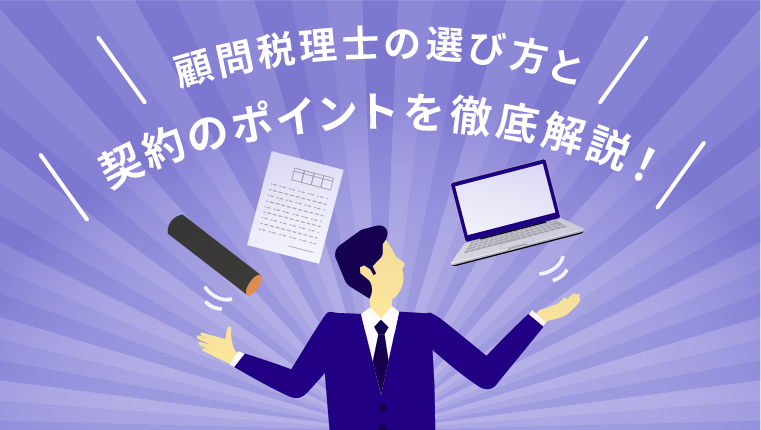
顧問税理士の選び方と契約のポイントを徹底解説!
-
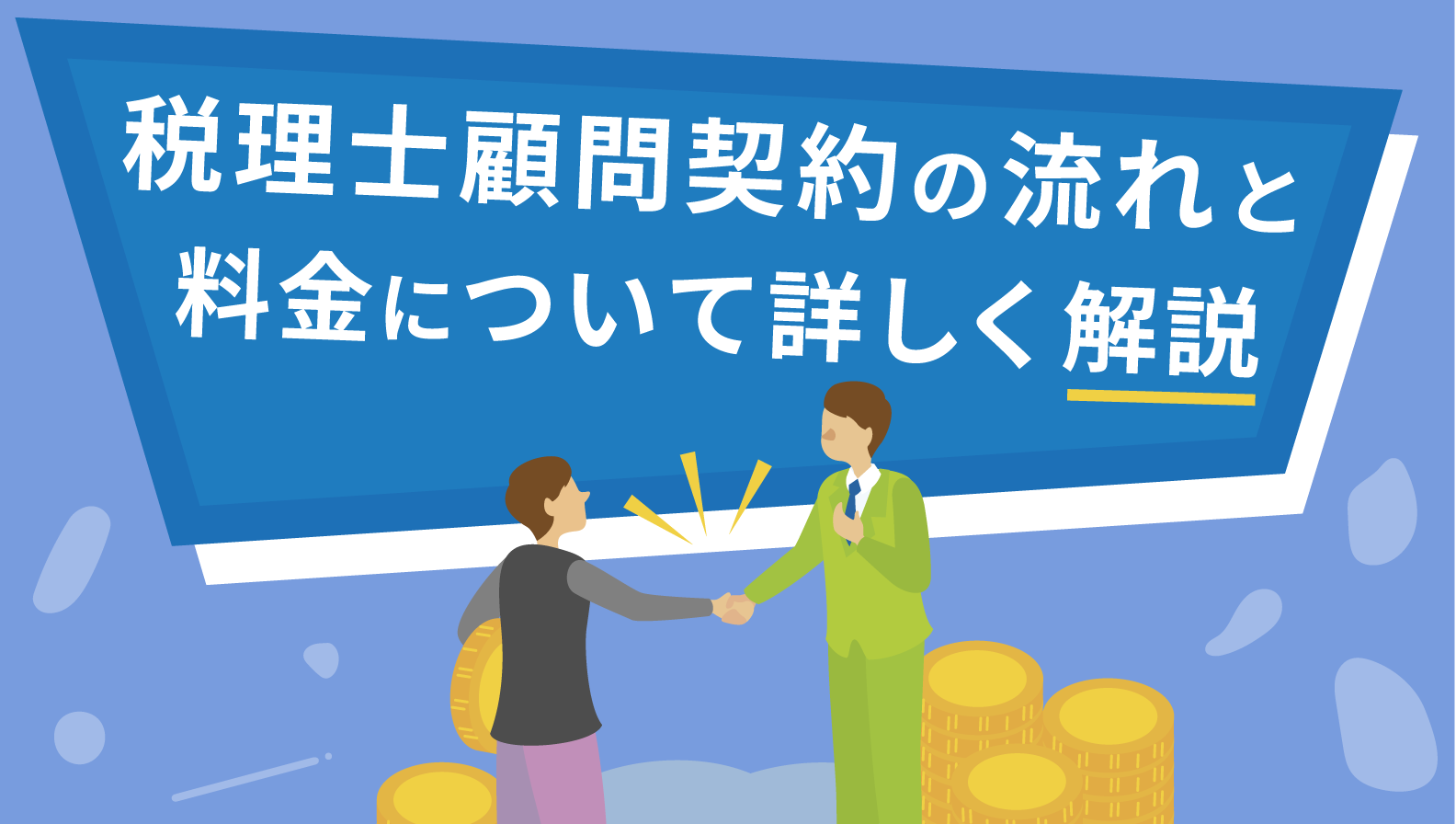
税理士顧問契約の流れと料金について詳しく解説
-
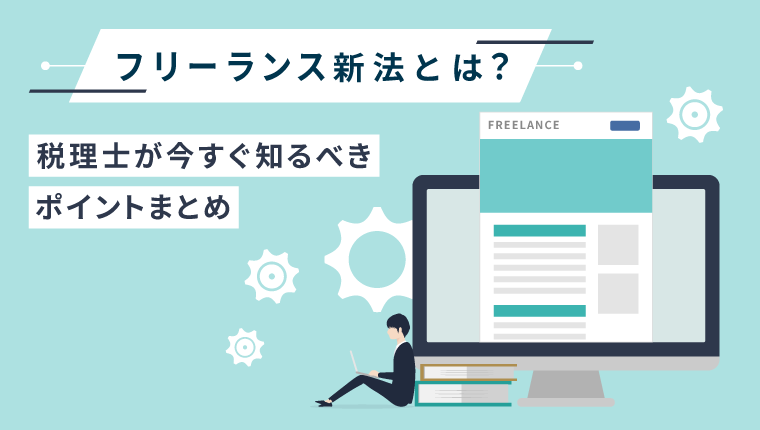
フリーランス新法とは?税理士が今すぐ知るべきポイントまとめ
公開日:2025/07/22
最終更新日:2025/08/01
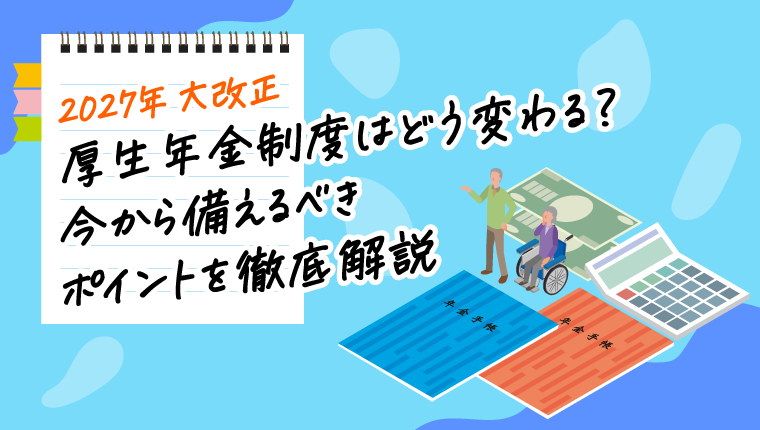
INDEX
2027年は、厚生年金制度にとって歴史的な転換点となる年です。令和7年(2025年)6月に成立した「年金制度改正法」により、2027年から段階的に実施される大規模な制度改革は、企業経営者から短時間労働者まで、あらゆる働く人の老後保障に大きな影響を与えます。特に2027年9月と10月には、厚生年金制度の根幹に関わる2つの重要な改正が同時に始まります。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
2027年改正の全体像
高所得者層への影響:標準報酬月額上限の引き上げ
2027年9月から、厚生年金の標準報酬月額上限が段階的に引き上げられます。現在65万円の上限が3年間で75万円まで引き上げられる計画です。
【表1】標準報酬月額上限の引き上げスケジュール
| 実施時期 | 上限額 | 現行からの増加額 | 対象年収(目安) |
|---|---|---|---|
| 2025年現在 | 65万円 | - | 約798万円 |
| 2027年9月 | 68万円 | +3万円 | 約834万円 |
| 2028年9月 | 71万円 | +6万円 | 約870万円 |
| 2029年9月 | 75万円 | +10万円 | 約920万円 |
この改正により、高所得者層の保険料負担が大幅に増加します。最終的に上限が75万円になった場合、月収75万円以上の方の保険料(本人負担分)は月約9,100円増加し、社会保険料控除を考慮すると実質的な負担増は月約6,100円となります。
短時間労働者への影響:適用拡大の加速
2027年10月からは、社会保険の適用拡大が本格化します。現在は従業員51人以上の企業で働く短時間労働者が対象ですが、段階的に企業規模要件が縮小されます。
【表2】企業規模要件の段階的撤廃スケジュール
| 実施時期 | 対象企業規模 | 新たな加入対象者数(推定) |
|---|---|---|
| 2025年現在 | 51人以上 | - |
| 2027年10月 | 36人以上 | 約20万人 |
| 2029年10月 | 21人以上 | 約30万人 |
| 2032年10月 | 11人以上 | 約40万人 |
| 2035年10月 | 全企業(要件撤廃) | 約50万人 |
「106万円の壁」撤廃の前倒し実施
2026年10月をめどに、厚生年金加入の賃金要件である「年収106万円の壁」が撤廃されます。これは2027年改正の前哨戦として位置づけられ、パートタイム労働者約200万人が新たに厚生年金の加入対象となります。
現在の加入要件は以下の通りです:
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)
・従業員51人以上の企業
・学生でないこと
賃金要件の撤廃により、週20時間以上働く短時間労働者は、企業規模と年収に関係なく厚生年金に加入することになります。
改正の背景と目的
社会経済情勢の変化への対応
少子高齢化の進行と働き方の多様化により、従来の年金制度では対応が困難な状況が生じています。特に以下の課題が顕在化しています。
・高所得者層の保険料負担の不公平性:現在の上限(65万円)を超える賃金を受け取る人は、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取れない状況
・短時間労働者の保障不足:非正規雇用者の増加により、十分な年金保障を受けられない労働者が増加
・企業規模による格差:同じ働き方でも企業規模により社会保険の適用が異なる不公平
制度の持続可能性確保
年金制度の財政基盤を強化するため、保険料収入の拡大と給付と負担の均衡確保が急務となっています。高所得者層の負担増と加入者の拡大により、制度全体の安定性を高めることが目的です。
企業への影響と対応
中小企業への段階的な影響
2027年10月から従業員36人以上の企業が適用対象となることで、多くの中小企業が初めて短時間労働者の社会保険加入義務を負うことになります。企業側の負担増への配慮として、以下の支援策が検討されています:
・労使折半となっている保険料を企業側がより多く負担できる仕組み
・段階的な実施による準備期間の確保
・既存の個人事業所(5人以上)については当面任意加入
人事労務管理の変更
企業は以下の対応が必要になります:
・時間管理の厳格化:週20時間以上の労働者の正確な把握
・給与体系の見直し:社会保険料負担を考慮した賃金設定
・従業員への説明:制度変更の周知と理解促進
・システム対応:給与計算システムの更新
働く人への影響
高所得者層(年収800万円以上)
負担増の詳細:
・2027年9月:月額約2,700円増
・2028年9月:さらに月額約2,700円増
・2029年9月:さらに月額約3,500円増(累計約9,100円増)
| 実施時期 | 上限額 | 現行からの増加額 | 対象年収(目安) | 保険料増加額(月額・本人分) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年現在 | 65万円 | - | 約798万円 | - |
| 2027年9月 | 68万円 | +3万円 | 約834万円 | +2,747円 |
| 2028年9月 | 71万円 | +6万円 | 約870万円 | +5,494円 |
| 2029年9月 | 75万円 | +10万円 | 約920万円 | +9,150円 |
メリット:
・10年間拠出を続けた場合、月約5,100円の年金増額(年金課税考慮後は月約4,300円)
・収入に見合った年金受給が可能
短時間労働者
新たな加入対象者の変化:
・2026年10月:賃金要件撤廃により約200万人が新規加入
・2027年10月以降:企業規模要件の段階的撤廃により順次拡大
| 実施時期 | 対象企業規模 | 新たな加入対象者数(推定) | 累計加入者数 | 企業数(推定) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年現在 | 51人以上 | - | 約200万人 | 約2万社 |
| 2027年10月 | 36人以上 | 約20万人 | 約220万人 | 約2.5万社 |
| 2029年10月 | 21人以上 | 約30万人 | 約250万人 | 約3.5万社 |
| 2032年10月 | 11人以上 | 約40万人 | 約290万人 | 約5万社 |
| 2035年10月 | 全企業(要件撤廃) | 約50万人 | 約340万人 | 約8万社 |
メリット:
・将来の年金受給額の増加
・傷病手当金、出産手当金などの給付拡充
・健康保険の保障充実
注意点:
・手取り収入の減少(社会保険料負担)
・働き方の選択肢への影響
労働時間別・年収別の影響シミュレーション
| 労働時間(週) | 時給 | 月収 | 年収 | 社会保険料(月額) | 手取り減少額 | 将来年金増額(月額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20時間 | 1,000円 | 8.7万円 | 104万円 | 約1.3万円 | 約1万円 | 約1.5万円 |
| 25時間 | 1,200円 | 13万円 | 156万円 | 約1.9万円 | 約1.5万円 | 約2.3万円 |
| 30時間 | 1,500円 | 19.5万円 | 234万円 | 約2.9万円 | 約2.3万円 | 約3.5万円 |
制度改正の課題と展望
実施上の課題
企業側の課題:
・中小企業の負担増への対応
・人事労務管理の複雑化
・システム投資の必要性
企業規模別の準備期間と対応課題
| 企業規模 | 適用開始 | 準備期間 | 主な対応課題 | 推定コスト増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 36-50人 | 2027年10月 | 2年6ヶ月 | システム導入、労務管理体制 | 3-5% |
| 21-35人 | 2029年10月 | 4年6ヶ月 | 人事制度整備、従業員教育 | 5-8% |
| 11-20人 | 2032年10月 | 7年6ヶ月 | 基本的な労務管理導入 | 8-12% |
| 1-10人 | 2035年10月 | 10年6ヶ月 | 零細企業の負担軽減策検討 | 10-15% |
労働者側の課題:
・短時間労働者の手取り収入減少
・働き方の選択肢制限
・制度理解の必要性
長期的な展望
2027年改正は、より公平で持続可能な年金制度の構築に向けた重要な第一歩です。今後も以下の課題に取り組む必要があります:
・基礎年金の給付水準底上げ:経済情勢を見極めた上で2029年以降に検討
・私的年金制度の充実:iDeCoの加入年齢引き上げなど
・在職老齢年金の見直し:働く高齢者の年金減額緩和
制度改正の財政効果と持続可能性
保険料収入の増加
短期的な効果(2027-2030年):
・標準報酬月額上限引き上げ:年間約1,500億円
・適用拡大:年間約3,000億円
・合計:年間約4,500億円の保険料収入増
長期的な効果(2030-2050年):
・制度の持続可能性向上
・給付水準の維持・向上
・世代間格差の縮小
給付費の変化
給付費の増加要因:
・新規加入者の年金受給権発生
・高所得者の年金額増加
・遺族年金の拡充
財政効果の試算(2030年時点)
| 項目 | 保険料収入増加 | 給付費増加 | 純効果 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額上限引き上げ | +1,500億円 | +300億円 | +1,200億円 |
| 適用拡大 | +3,000億円 | +800億円 | +2,200億円 |
| その他の改正 | +500億円 | +200億円 | +300億円 |
| 合計 | +5,000億円 | +1,300億円 | +3,700億円 |
制度の持続可能性への貢献
所得代替率の維持:現在の所得代替率61.7%を将来にわたって維持・向上させる効果が期待されます。
積立金の活用: 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用資産約200兆円の効率的な活用により、制度の安定性を確保します。
国際比較と日本の特徴
諸外国の年金制度改革
アメリカ:
・社会保障税の上限引き上げ(2023年:$160,200)
・満額支給開始年齢の段階的引き上げ
ドイツ:
・保険料率の段階的引き上げ(18.6% → 20%)
・私的年金の拡充(リースター年金)
フランス:
・受給開始年齢の引き上げ(62歳 → 64歳)
・拠出期間の延長(41年 → 43年)
主要国の年金制度改革比較
| 国名 | 主な改革内容 | 実施時期 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 適用拡大、上限引き上げ | 2027年~ | 段階的・包括的 |
| アメリカ | 上限引き上げ | 継続的 | 税制との連動 |
| ドイツ | 保険料率引き上げ | 2023年~ | 負担増重視 |
| フランス | 受給年齢引き上げ | 2023年~ | 給付抑制重視 |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
2027年の厚生年金大改正は、日本の年金制度にとって歴史的な転換点となります。高所得者層の負担増と短時間労働者の加入拡大により、より公平で持続可能な制度への変革が進みます。
企業にとっては人事労務管理の大幅な見直しが必要となり、働く人にとっては老後保障の充実と現在の負担増のバランスを考えた働き方の検討が重要になります。制度改正の詳細を理解し、適切な準備を進めることで、変化する年金制度を有効活用することが可能となるでしょう。
2027年改正の成功は、日本の超高齢社会における社会保障制度の持続可能性を左右する重要な要素となります。労使双方の理解と協力により、全世代が安心できる年金制度の実現を目指していく必要があります。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)