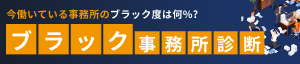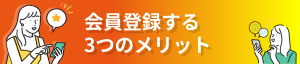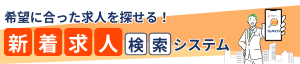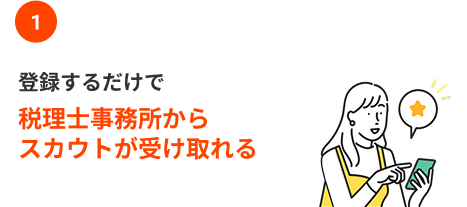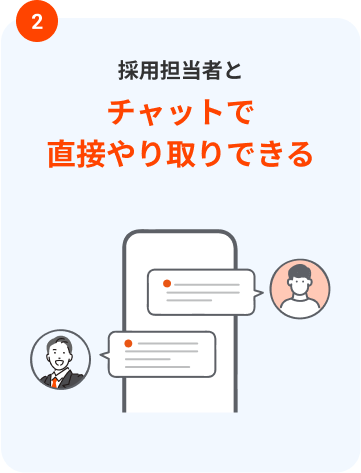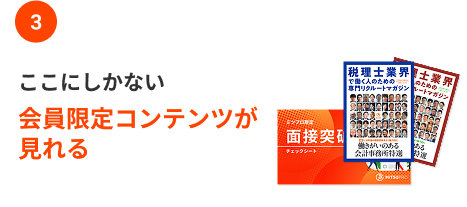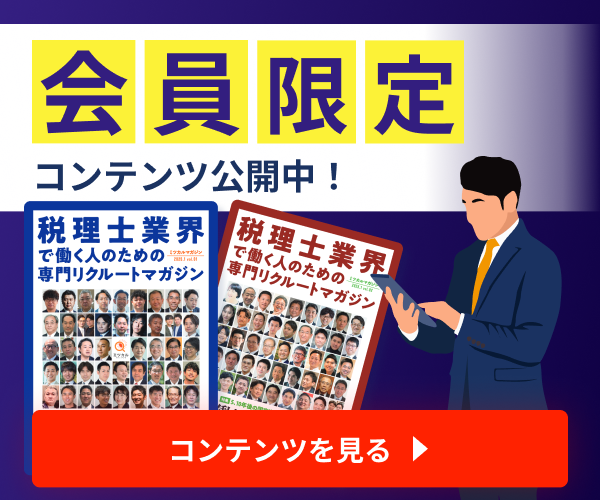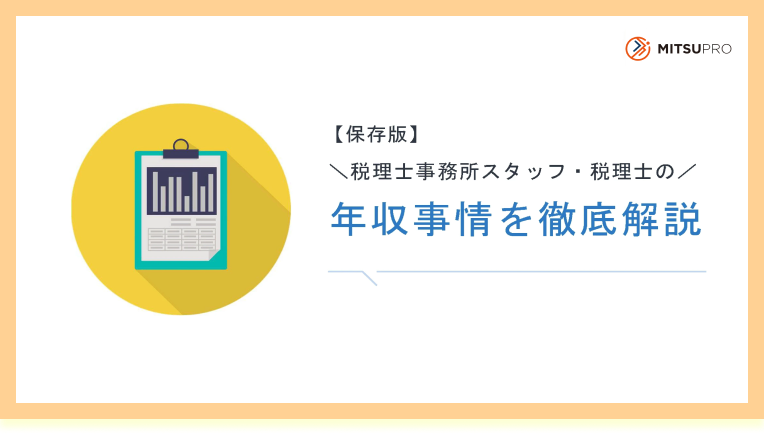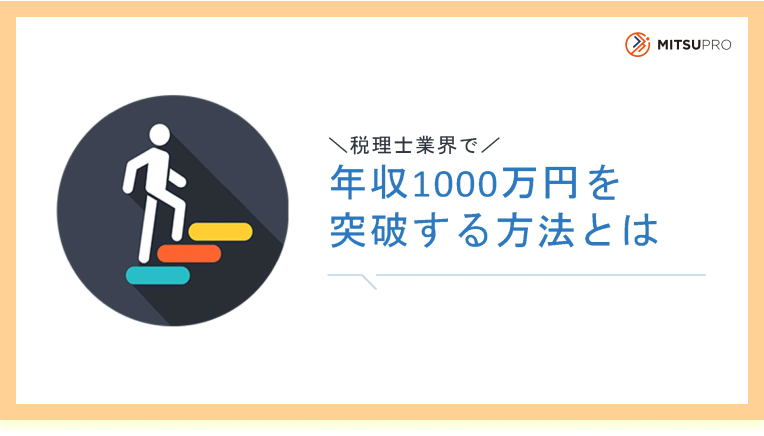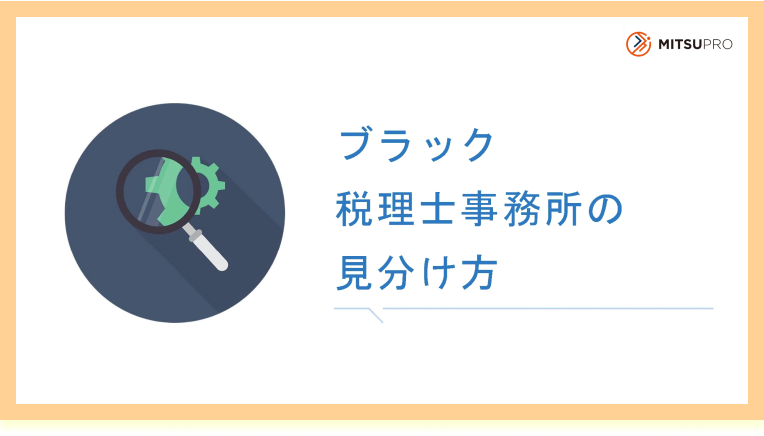INDEX
おすすめ記事
-
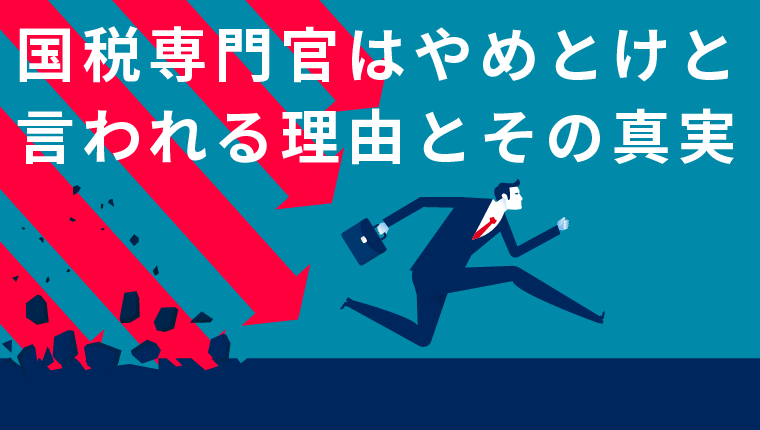
国税専門官はやめとけと言われる理由とその真実
-
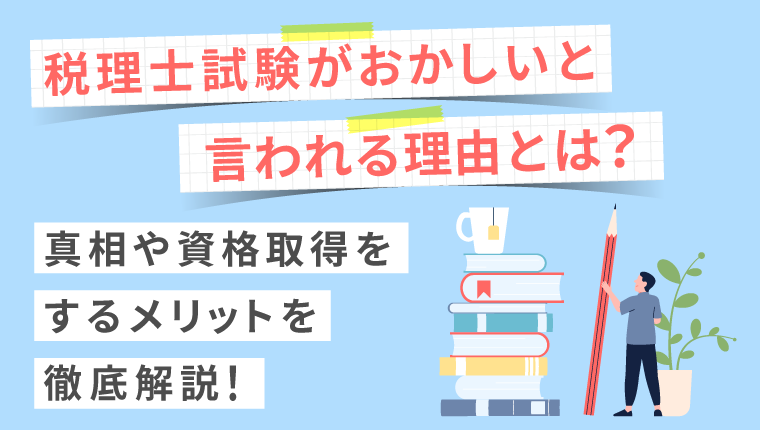
税理士試験がおかしいと言われる理由とは?真相や資格取得をするメリットを徹底解説!
-
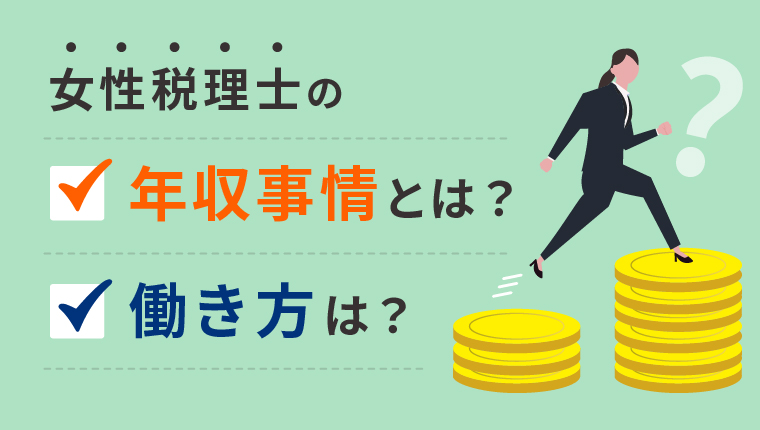
女性税理士の年収事情とは?働き方は?
-

税務会計とは?財務会計との違いを徹底解説!
-
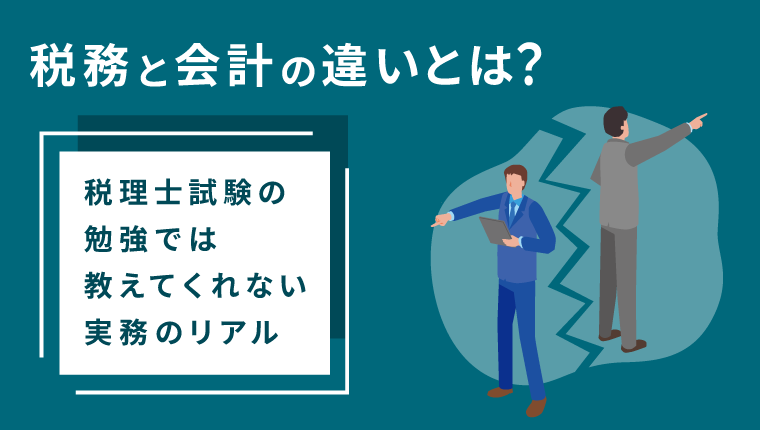
税務と会計の違いとは?税理士試験の勉強では教えてくれない実務のリアル
公開日:2025/07/18
最終更新日:2025/08/01
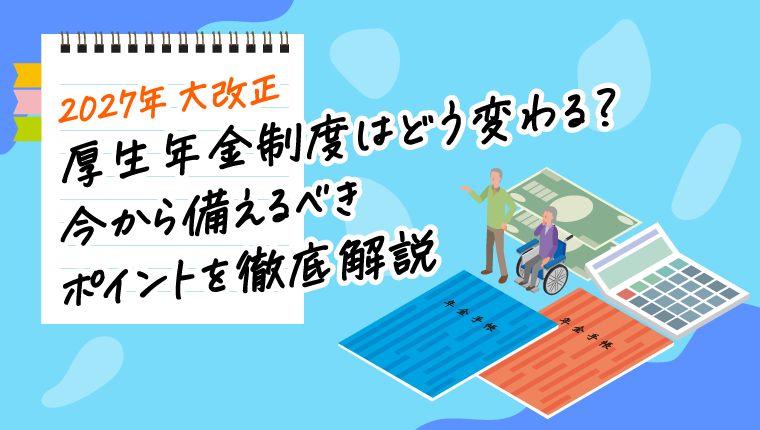
INDEX
2025年7月1日、国税庁より令和7年分の路線価が発表されました。全国平均で2.7%上昇し、4年連続の上昇となっています。インバウンド需要の回復や都市部の不動産価格高騰が主な要因となり、相続税や贈与税の計算にも大きな影響を与えることが予想されます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
路線価とは何か
路線価とは、毎年7月上旬に国税庁から公表される土地の評価指標で、路線(道路)に面した宅地の1㎡あたりの価額を示したものです。これは毎年1月1日時点での価格を基準として算定されており、相続税や贈与税における土地の評価額を算定する際の重要な基準価格として活用されています。
路線価は不動産売買における実勢価格(時価)や固定資産税評価額とは異なる独自の評価体系を持っており、一般的に実勢価格の約80%程度の水準で設定されています。これは相続税や贈与税の計算において、納税者の負担を一定程度軽減する配慮からこのような水準が設定されているためです。
2025年路線価の概要
全国的な動向
2025年7月1日、国税庁が令和7年分の路線価を公表しました。全国約32万地点の標準宅地における全国の平均変動率は、前年から2.7%のプラスとなり、4年連続での上昇となりました。これは新型コロナウイルスの影響で一時的に下落した路線価が、経済活動の正常化とともに回復基調を続けていることを示しています。
特に注目すべきは、この上昇率が前年の水準を上回っており、土地価格の上昇トレンドが加速していることです。現行の調査方法が始まった2010年以降でも、このような継続的な上昇は特筆すべき現象といえます。
都道府県別の状況
都道府県別の詳細を見ると、前年から上昇したのは35都道府県となり、前年の29都道府県から6県増加しました。一方で下落した都道府県は12県(前年16県)と減少しており、全国的に路線価の底上げが進んでいることが確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 上昇率 | 前年比較 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | +8.1% | 前年+4.2%から大幅上昇 |
| 2 | 沖縄県 | +6.3% | 観光需要回復の影響 |
| 3 | 神奈川県 | +5.2% | 東京への近接性が評価 |
| 4 | 埼玉県 | +4.8% | 都心へのアクセス利便性 |
| 5 | 千葉県 | +4.5% | 住宅需要の高まり |
| 6 | 大阪府 | +3.8% | 関西圏の経済活動活発化 |
| 7 | 京都府 | +3.5% | 観光地としての価値向上 |
| 8 | 愛知県 | +3.2% | 製造業の回復 |
| 9 | 福岡県 | +2.9% | 九州経済の中心地 |
| 10 | 北海道 | +2.7% | 観光地・リゾート地の高騰 |
最も下落率が大きかったのは奈良県の-1.0%でした。能登半島地震の影響が初めて反映された地域もありましたが、全体的には経済回復の恩恵を受けた地域が多数を占めています。
最高路線価の動向
全国で最も路線価が高いのは、40年連続で東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りであり、1㎡あたり4,808万円となりました。これは前年から384万円上昇しており、上昇率は8.7%に達しています。5年ぶりに過去最高額を更新したことで、銀座エリアの商業地としての価値の高さを改めて示す結果となりました。
| 都道府県 | 所在地 | 最高路線価(万円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 4,808 | +8.7% |
| 大阪府 | 大阪市北区角田町 御堂筋 | 1,696 | +3.2% |
| 愛知県 | 名古屋市中区栄3丁目 中央通り | 1,120 | +0.0% |
| 神奈川県 | 横浜市西区南幸1丁目 駅前通り | 1,040 | +4.0% |
| 福岡県 | 福岡市中央区天神2丁目 渡辺通り | 1,000 | +4.2% |
| 北海道 | 札幌市中央区北5条西 駅前通り | 652 | +2.8% |
| 京都府 | 京都市下京区四条通 寺町東入 | 640 | +3.2% |
| 兵庫県 | 神戸市中央区明石町 明石町筋 | 528 | +3.0% |
| 埼玉県 | さいたま市大宮区桜木町 中央通り | 520 | +4.0% |
| 千葉県 | 千葉市中央区富士見 富士見通り | 456 | +3.6% |
路線価上昇の背景要因
インバウンド需要の回復
今回の路線価上昇の最大の要因として、インバウンド需要の本格的な回復が挙げられます。新型コロナウイルスの影響で一時的に減少していた訪日外国人観光客が急速に回復し、観光地や繁華街での商業活動が活発化しています。
特に上昇率の高い地点を見ると、長野県白馬村(32.4%)、北海道富良野市(30.2%)、東京都浅草(29.0%)といった著名な観光地が上位を占めており、観光需要の回復が直接的に地価上昇に反映されていることが分かります。
都市部の不動産投資増加
都市部、特に東京都心部では、海外や地方からの人口流入に伴うマンション需要の増加が顕著に表れています。テレワークの普及により一時的に都心離れが進んだものの、経済活動の正常化とともに都心回帰の動きが加速しており、これが不動産価格の上昇を牽引しています。
また、観光地では、ホテルやコンドミニアムなどの建設が相次いでおり、インバウンド需要の長期的な成長を見込んだ不動産投資の増加も路線価上昇の一因となっています。
金融政策の影響
長期間続いた低金利政策により、不動産投資に対する資金調達コストが低く抑えられていることも、不動産価格上昇の背景にあります。これにより、個人投資家から機関投資家まで、幅広い層で不動産投資が活発化しており、需要の底上げに寄与しています。
相続税・贈与税への影響
相続税評価額の上昇
路線価の上昇は、相続税や贈与税の計算において土地の評価額を直接的に引き上げることになります。特に都市部で土地を所有している場合、相続税の負担が数十万円単位で増加する可能性があります。
相続税への影響例
東京都内の100坪の土地を相続する場合、路線価が8.1%上昇することで、相続税評価額が大幅に増加し、相続税額に直接影響を与えます。具体的な税額は他の相続財産や法定相続人の数によって変動しますが、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分について課税されるため、土地の評価額上昇は税負担の増加に直結します。
生前贈与への影響
路線価の上昇は贈与税の計算にも影響を与えます。土地を生前贈与する場合、その評価額は路線価を基準として算定されるため、路線価の上昇は贈与税の増加につながります。特に相続時精算課税制度を利用している場合、贈与時の評価額が将来の相続税計算にも影響するため、慎重な判断が必要です。
対策の必要性
路線価の継続的な上昇を受けて、以下のような対策を検討することが重要です:
・小規模宅地等の特例の活用検討
・生前贈与の時期とタイミングの最適化
・相続時精算課税制度の活用
・土地の有効活用による評価額の圧縮
・生命保険の活用による相続税対策
地域別の詳細分析
東京都の状況
東京都は全国で最も高い8.1%の上昇率を記録しており、都心部を中心とした価格上昇が顕著です。特に商業地域や住宅地域を問わず、交通アクセスの良好な地域で大幅な上昇が見られます。銀座、新宿、渋谷などの主要繁華街では、インバウンド需要の回復と商業活動の活発化が直接的に地価上昇に反映されています。
観光地の状況
観光地では特に大きな上昇率を記録しています。北海道富良野市や長野県白馬村などのリゾート地では、30%を超える上昇率となっており、インバウンド需要の回復が地価に与える影響の大きさを示しています。これらの地域では、宿泊施設の建設ラッシュや観光関連サービスの拡充が進んでおり、土地需要の増加が続いています。
地方都市の動向
地方都市でも、県庁所在地を中心として路線価の上昇が見られます。地方への移住促進政策や企業の地方展開などにより、一部の地方都市では都市部に匹敵する上昇率を記録している地域もあります。
今後の見通しと対策
今後の路線価の動向は、短期的には金融政策やインバウンド需要、物価上昇といった要因が価格を下支えし、全国的に緩やかな上昇が見込まれます。特に大阪・関西万博の開催に伴い、関西圏の地価上昇が顕著になる可能性があります。
中期的には、人口減少や団塊世代の相続による不動産供給の増加、技術革新や環境政策が市場に影響を与え、都市部と地方の格差拡大が続く見通しです。一部の郊外や地方では価格調整の可能性がありますが、東京圏などの都市部は堅調さを維持すると考えられます。
長期的には人口減少が本格化し、空き家率の上昇や都市機能の再編が進むことで、全国的な地価の平均は横ばいか微減となる見込みです。一方、外国人投資家の需要や社会保障政策の変化により、都市部では一定の価格維持・上昇が期待され、郊外や地方部では更なる下落圧力が高まると見られます。
短期的見通し(2025年下半期~2026年)
・政策金利の影響:日銀は段階的な利上げを進行中(0.5%程度まで)、住宅ローンや投資利回りに影響。
・インバウンド需要:訪日客4,000万人目標+万博開催で関西圏を中心に観光需要増。
・物価上昇:CPI上昇率2%程度。新築価格上昇 → 既存不動産にも好影響。
予測まとめ
・全国平均上昇率:+1.5〜2.5%
・関西圏は+3〜5%
・都市部と地方の格差拡大傾向
中期的見通し(2027年~2030年)
・人口動態の変化:人口1.2億人を下回る → 地方では需要減少・地価下落圧力。
・相続不動産の供給増:団塊世代の相続本格化 → 郊外・地方で供給過多。
・技術革新:リモートワーク拡大 → 郊外住宅需要は分散、オフィス需要減。
・環境政策:省エネ性能高い物件の価値上昇、古い物件は路線価下落要因に。
予測まとめ
・全国平均上昇率:0〜1.5%
・地域格差は東京圏と地方で2倍以上
・都市部の好立地は価値維持
長期的見通し(2030年以降)
・人口減少の本格化:2050年に1億人未満。地方では空き家率50%超も。
・社会保障と税制:税制改正・相続税改革の可能性、不動産活用促進策も。
・海外投資家の動向:東京・大阪・京都に注目、価格下支え要因となる。
・都市機能の再編:コンパクトシティ化 → 都市中心部は地価維持、郊外は大幅下落へ。
予測まとめ
・全国平均:-0.5〜+0.5%/年
・都市中心 vs 郊外・地方の二極化進行
・空き家問題深刻化、海外資本が都市部を支える
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
2025年の路線価は4年連続の上昇となり、全国平均で2.7%の増加を記録しました。インバウンド需要の回復、都市部の不動産投資増加、金融政策の影響などが主な要因として挙げられます。
特に東京都では8.1%の高い上昇率を記録し、銀座の最高路線価は1㎡あたり4,808万円と過去最高額を更新しました。この上昇トレンドは相続税や贈与税の計算に直接影響を与えるため、土地を所有する方は適切な税務対策を検討することが重要です。
今後も都市部や観光地を中心とした路線価の上昇が予想されるため、早期の対策立案と専門家との相談が推奨されます。路線価の動向を注視しながら、最適な相続税対策を実施することで、税負担の軽減と円滑な資産承継を実現することが可能です。

平川 文菜(ねこころ)