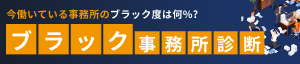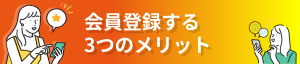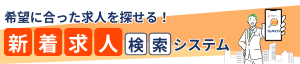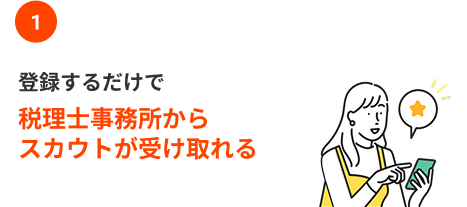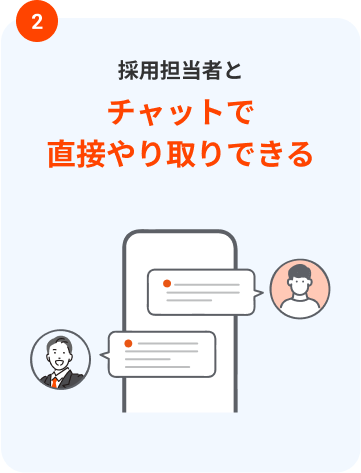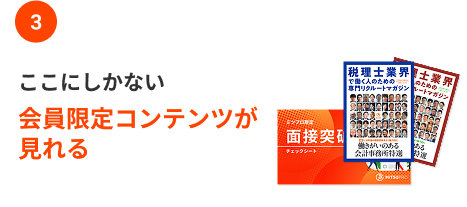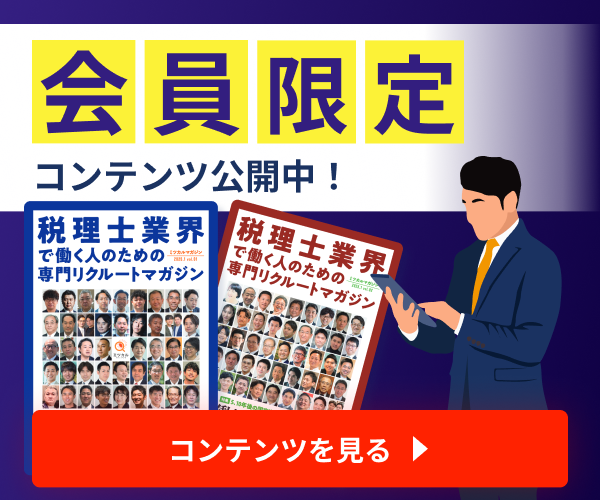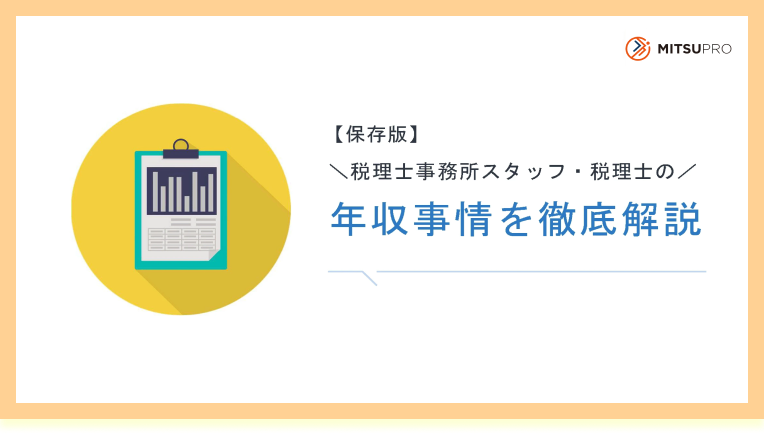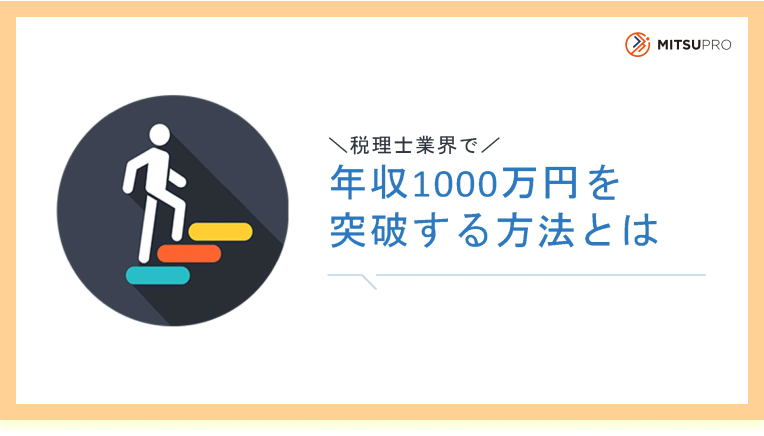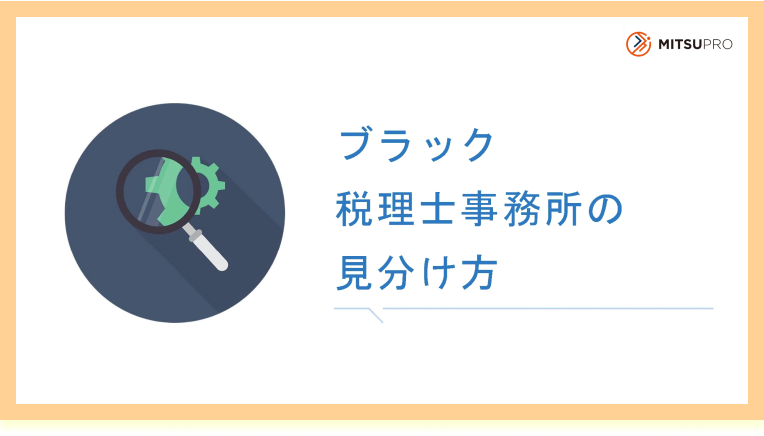INDEX
おすすめ記事
-
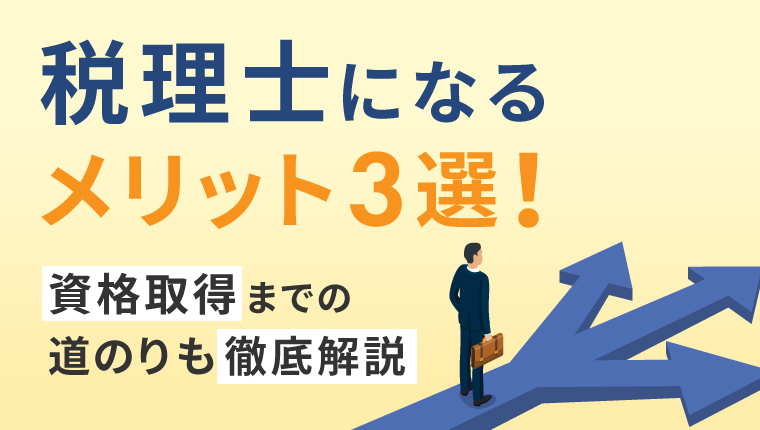
税理士になるメリット3選!資格取得までの道のりも徹底解説
-
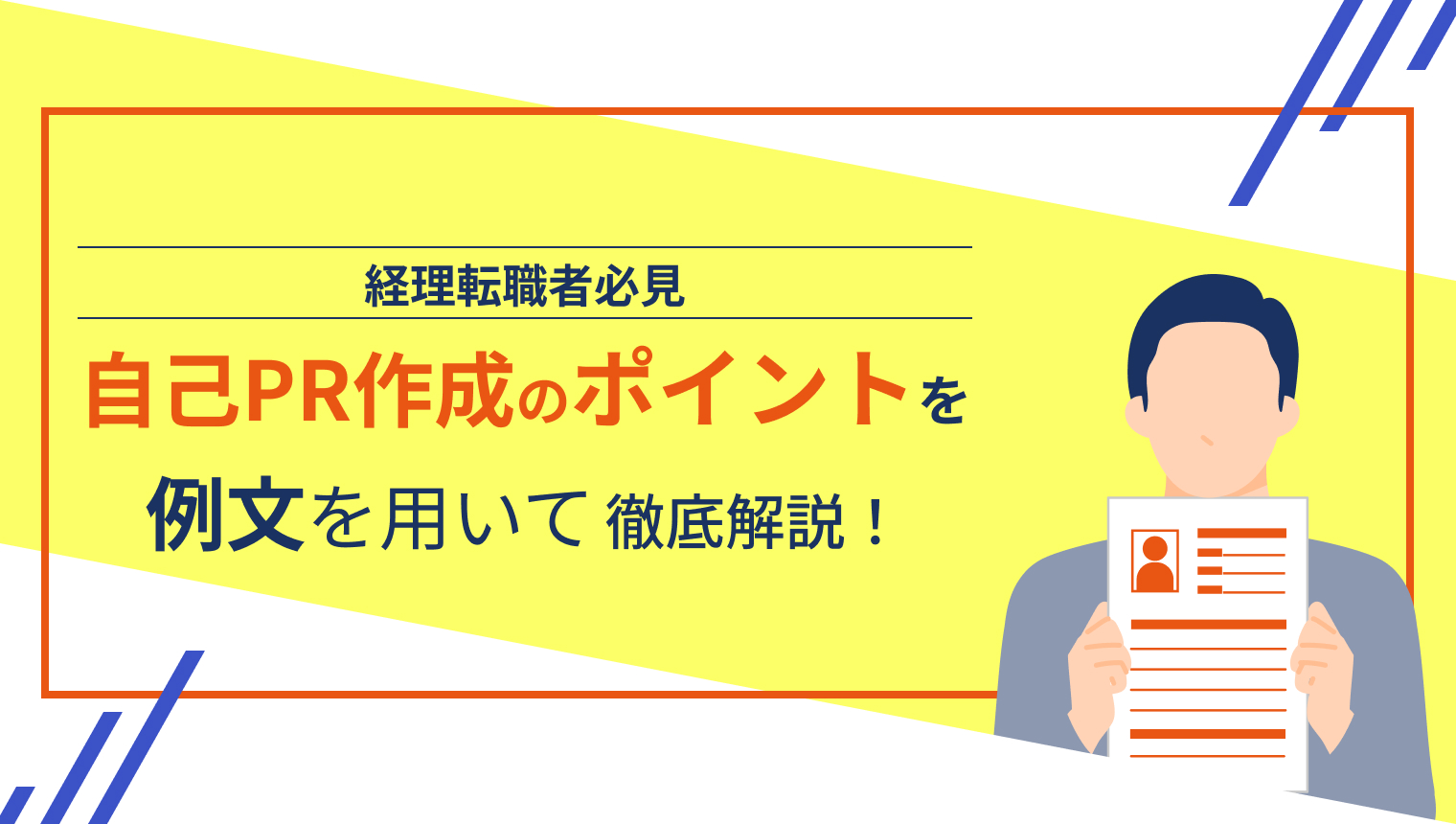
【経理転職者必見】自己PR作成のポイントを例文を用いて徹底解説!
-

税理士顧問料の値上げの理由やタイミングは?
-
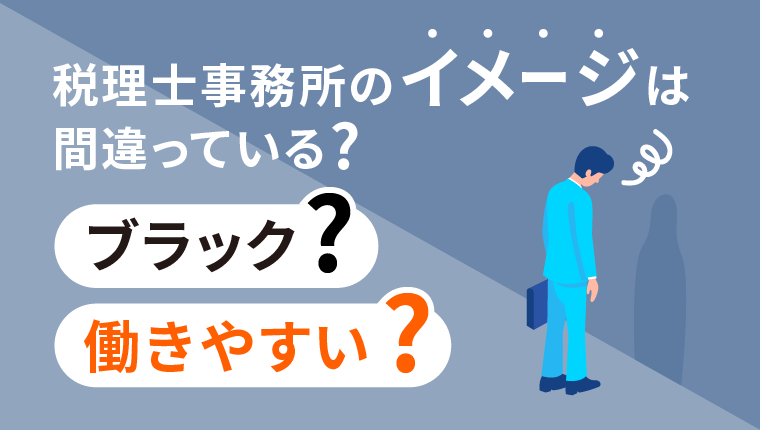
税理士事務所のイメージは間違っている?ブラック?働きやすい?
-
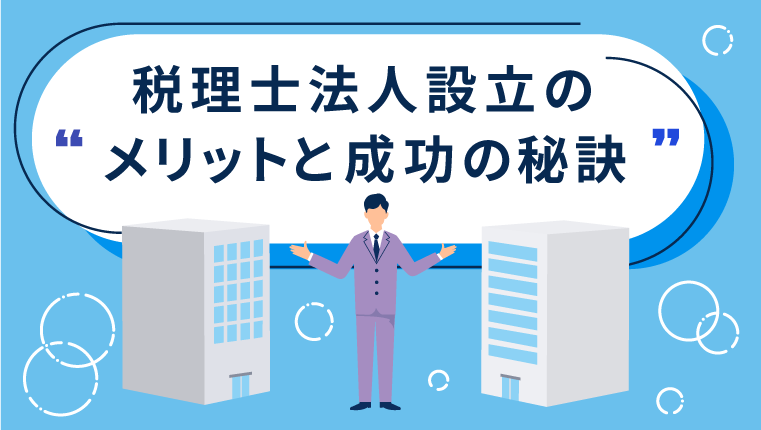
税理士法人設立のメリットと成功の秘訣
公開日:2025/06/18
最終更新日:2025/08/24
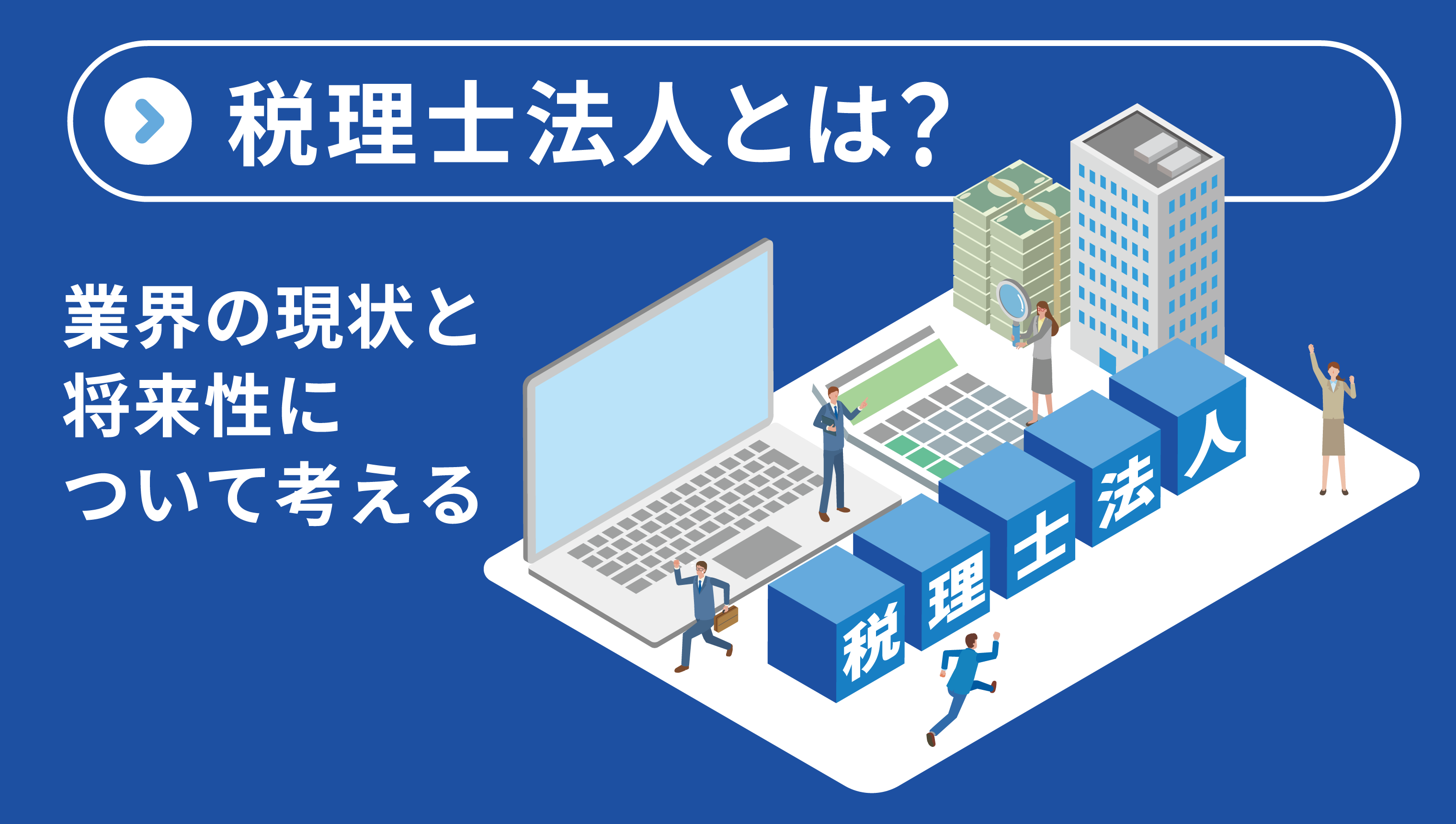
INDEX
「税理士法人」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?
個人で開業する“町の税理士”とは異なる、もうひとつの税理士のカタチ。
それは、複数の税理士がチームを組み、法人格をもって運営されるプロフェッショナル集団です。
2002年に誕生した税理士法人は、いまや日本の税務サービスの中核を担っています。
設立条件、責任の重さ、業務範囲、キャリアの展望──その仕組みは意外と知られていません。
個人事務所との違いは? どんな人が働いていて、どんな未来が描けるのか?
この記事では、税理士法人の定義からキャリアの可能性まで、体系的にわかりやすく解説します。
「税理士法人って、なんだか難しそう…」と思っていた方にこそ、読んでいただけましたら幸いです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士法人とは?
税理士法人は、税理士法に基づいて設立される法人で、税理士が共同で税務業務を行うための組織形態です。2001年の税理士法改正により創設されました。
税理士法人の基本的な定義と特徴
税理士法人とは、複数の税理士が共同で業務を行うために設立される法人形態で、税理士法第43条以降にその根拠があります。設立には社員税理士(構成員)を最低2名以上必要とし、個人の税理士と同様に、税務代理、税務書類の作成、税務相談などの業務を行うことができます。
税理士法人には法人格があり、「税理士法人〇〇」という法人名で登記されます。ただし、社員税理士は無限責任を負う仕組みとなっており、業務上の過失による損害には個人としても責任を負う点に注意が必要です。
また、法人として登記されているため、構成する税理士が1人辞めたり死亡したとしても、法人自体は存続できます。これにより、事業承継や法人運営の安定性に優れた組織形態となっています。
| 項目 | 内容 |
| 設立根拠 | 税理士法第43条以下 |
| 構成員 | 税理士2名以上(社員税理士として登録) |
| 業務範囲 | 個人税理士と同様に、税務代理・税務書類の作成・税務相談等 |
| 法人格 | 有り(法人として登記) |
| 名称 | 「税理士法人◯◯」という法人名が必要 |
| 責任 | 無限責任(社員税理士が損害賠償責任を負う) |
| 継続性 | 法人であるため、1人の税理士が引退・死亡しても継続可能 |
税理士事務所との違い
税理士法人と税理士事務所(個人開業の税理士)は、いずれも税務業務を行いますが、その組織形態や法的性質、経営の安定性に大きな違いがあります。
税理士法人は法人格を有し、構成員である税理士(社員税理士)が共同で運営を行うため、一定の規模や分業体制が整っています。一方、個人の税理士事務所は、税理士1人でも開設でき、柔軟な対応やコストを抑えた運営が可能です。ただし、税理士が死亡・引退すると事務所は原則的に消滅するため、継続性には課題があります。
税理士法人のほうが、法人としての信用力や人材育成、事業承継のしやすさに優れている一方、個人事務所は小回りの利く丁寧なサービスを提供しやすい点が強みです。
| 項目 | 税理士法人 | 税理士事務所(個人事業) |
| 組織形態 | 法人 | 個人事業 |
| 法人格 | 有り | 無し |
| 開設条件 | 社員税理士2名以上が必要 | 税理士資格があれば1人でも開設可能 |
| 代表名称 | 「税理士法人◯◯」など法人名 | 「◯◯税理士事務所」など個人名が多い |
| 継続性 | 税理士が退任しても法人は存続 | 税理士の引退・死亡で原則終了 |
| 信頼性・規模感 | 組織力があるため信頼性が高く、規模も大きい傾向 | フットワークが軽く、個別対応に強いことも |
税理士法人の業務内容
税理士法人が行える業務は、税理士法に基づく業務に限られます。大きく分けると次の3つが基本です。
| 業務区分 | 内容 |
| 税務代理 | 納税者の代理人として税務署とのやり取り(申告・更正の請求・税務調査の対応など)を行う |
| 税務書類の作成 | 確定申告書、相続税申告書、届出書類などの作成 |
| 税務相談 | 節税、相続対策、税務調査対応などの助言やアドバイス |
これに加え、以下のような周辺業務も多くの法人で行われています。
・記帳代行や経理支援(会計業務)
・経営計画・資金繰りのアドバイス
・会社設立支援
・相続・事業承継コンサルティング
・M&Aや組織再編サポート(大手税理士法人など)
会計業務と監査の役割
税理士法人は公認会計士とは異なり、監査報告書を発行する「法定監査」は行いません。ただし以下のような実質的な会計・チェック業務は担います。
| 区分 | 税理士法人での役割 |
| 会計業務 | 会計ソフトへの入力代行、月次試算表・決算書の作成支援、経理体制の整備 |
| 自主監査的役割 | 決算前レビュー、経理処理の妥当性のチェック、税務リスクの洗い出しなど |
※上場企業の「監査」は、あくまで監査法人(=公認会計士)が実施する業務です。税理士法人が担当するのは税務上の視点からのレビューやアドバイスになります。
税理士法人で働くメリット
税理士法人は、個人の税理士事務所と比べて組織としての教育体制や業務分担、キャリア形成の機会が整っているのが特徴です。
| メリット | 内容 |
| 幅広い経験 | 相続、法人税、国際税務、M&A支援など、さまざまな分野の案件に携われる |
| 教育・研修制度 | 新人研修・税務勉強会・外部セミナーへの参加支援などが充実している法人も多い |
| チーム制による働き方 | 経験の浅い人でも先輩に相談しやすく、責任の重い業務を段階的に学べる |
| キャリアの選択肢 | ゆくゆくは社員税理士になって経営側に加わる道や、専門特化(資産税・国際税務など)の道もある |
| ワークライフバランス | 大手法人ではフレックス制度や在宅勤務制度を整備しているケースも多い |
税理士法人の設立と運営
設立の手続きと必要な条件
税理士法人を設立するには、税理士法に基づいた登録と登記が必要です。主な条件と流れは以下の通りです。
【設立の条件】
| 項目 | 内容 |
| 社員数 | 社員税理士が2名以上必要(税理士資格を有し、法人の構成員となる) |
| 資格要件 | 社員は全員、税理士登録をしていることが必須 |
| 名称規制 | 名称に「税理士法人」を含める必要がある |
| 兼業禁止 | 他士業法人(弁護士法人、公認会計士監査法人など)との兼業は不可 |
| 事務所 | 事務所所在地が定まっていることが必要 |
【設立手続きの流れ】
1.設立発起人(社員税理士)による協議・合意
2.定款の作成(公証人の認証は不要)
3.税理士会への設立申請
◦日本税理士会連合会(税理士法人設立登録申請書の提出)
4.税理士会の審査・登録
5.法務局への法人登記
6.国税・都道府県税への届出
※登録免許税は6万円(資本金関係なし)
運営上の注意点と社会的役割
【運営上の注意点】
| 注意点 | 解説 |
| 税理士法の遵守 | 無資格者への業務委託や非税理士の業務従事などは禁止 |
| 社員の責任 | 無限責任社員のため、損害賠償請求などに対して個人責任を負う |
| 登録事項の変更届出 | 役員の変更、事務所移転などは随時、税理士会へ届け出が必要 |
| 独立・退職時の対応 | 社員税理士が1人になると法人資格を喪失するため、最低2名体制の維持が必須 |
| 税務以外の業務制限 | コンサル業務などの展開には税務業務の延長線上であることが求められる(許容範囲に注意) |
【税理士法人の社会的役割】
税理士法人は、単なる「税務処理の代行業者」ではなく、企業や個人の経済活動を支えるパートナーとしての責任があります。
| 項目 | 役割 |
| 税務の専門家集団として | 正確な税務処理と納税の適正化を通じて、税務コンプライアンスの向上に貢献 |
| 中小企業の経営支援 | 決算対策・資金調達支援・事業承継など、経営面からのサポートも |
| 地域貢献 | 地域密着型の税理士法人は、地元経済の活性化や相談窓口としても機能 |
| 公共性の担保 | 税理士法に基づく職責から、高い倫理性と守秘義務が求められる専門職 |
税理士法人でのキャリア
就職や転職におけるポイント
税理士法人は規模や業務内容によって大きく特徴が異なるため、自分の志向に合った法人を選ぶことが重要です。
【チェックすべきポイント】
| 観点 | チェック内容 |
| 法人の規模 | Big4のような大手、地域密着型の中小法人、専門特化型法人など |
| 主な顧客層 | 上場企業・外資系企業 or 中小企業・個人事業主など |
| 業務内容 | 法人税メイン/資産税特化/国際税務対応/会計業務重視など |
| 教育体制 | OJTの有無、定期的な研修、勉強会の実施など |
| 資格取得支援 | 試験休暇、残業の少なさ、受験費用補助の有無など |
| キャリアパス | 使用人税理士→社員税理士への昇格制度の有無、役職制度など |
| 働き方 | 在宅制度、フレックス制度、繁忙期の残業の程度など |
【転職希望者が重視されやすい点】
・実務経験(法人税、所得税、消費税)
・クライアントとの折衝経験
・会計ソフトや税務申告ソフトの使用スキル(弥生、達人、TKC、勘定奉行など)
・コミュニケーション能力と誠実性
税理士法人でのキャリアパスと成長
以下では、税理士法人でのキャリアについて「キャリアの全体像」「具体的な職位と役割」「成長ステップ」「専門分野への展開」「働き方と待遇の実情」まで、体系的に詳しく解説します。
税理士法人でのキャリアは、大きく以下のような段階的ステップで形成されます。
1.スタッフ(未経験者・試験受験者)
2.シニアスタッフ/担当者
3.マネージャー(使用人税理士含む)
4.社員税理士(共同経営者)
5.代表社員(代表税理士)
その過程で、自らの専門領域やマネジメント力を磨きながら、経営層への道や独立の道を選ぶことができます。
職位別:具体的な役割と期待されるスキル
| 職位 | 役割・業務内容 | 必要スキル・経験 |
| スタッフ | 記帳代行、申告書作成補助、資料整理など | 基本的な会計知識、PCスキル、素直さと吸収力 |
| シニアスタッフ | クライアント担当、申告業務の主担当、簡易な相談対応 | 税務知識と実務経験、対人スキル |
| マネージャー | チーム管理、複雑な案件処理、品質管理、若手育成 | 幅広い税務知識、マネジメント能力 |
| 使用人税理士 | 税理士資格を活かして高難度業務に従事、顧客の主担当 | 資格 + 実務力、信頼構築力 |
| 社員税理士 | 経営判断、新規営業、人材採用・育成、法人の戦略構築 | 経営的視点、リーダーシップ、高い倫理観 |
成長のステップと期間イメージ
・入社1〜3年目:実務経験を積みながら税理士試験に挑戦
・3〜5年目:クライアントを持ち、申告実務の主担当へ
・5〜8年目:マネージャーへ昇格、チームを持つ
・10年目以降:社員税理士として経営参画、または独立
※大手と中小でスピード感や役職要件は異なります。
専門性の深堀りによるキャリアの幅
税理士法人では、以下のような専門分野に特化してキャリアを伸ばす道もあります。
| 専門領域 | 主な業務内容 |
| 資産税 | 相続税、贈与税、財産評価、事業承継対策など |
| 国際税務 | 外資系企業の税務、移転価格、BEPS対応など |
| 組織再編 | M&A、会社分割、合併、持株会社化など |
| 医療・学校法人 | 非営利法人特有の税務と会計制度対応 |
| 税務調査対応 | 重加算税のリスクマネジメント、折衝 |
特に大手税理士法人では、部署ごとに専門分野が分かれていることが多く、希望すれば異動・選抜によって高度な知見を積むことができます。
◆ キャリア後半の選択肢
税理士法人でスキルを積んだ後は、以下のような選択肢が視野に入ります。
・独立開業(法人から顧客を引き継ぎ開業)
・法人内のパートナー化(社員税理士昇格)
・経営コンサル・M&Aファームへの転職
・事業会社のCFO、経理部長、税務部門責任者
・講師・著者・YouTuberなど発信者として独自ブランドを築く
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士法人とは -まとめ
この記事では「税理士法人とは?」について解説させていただきました。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)