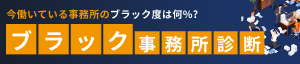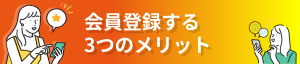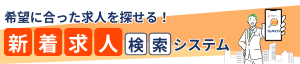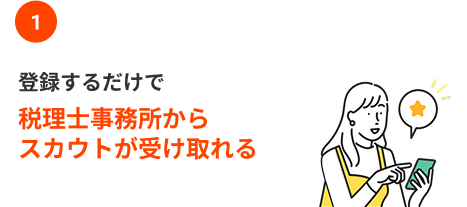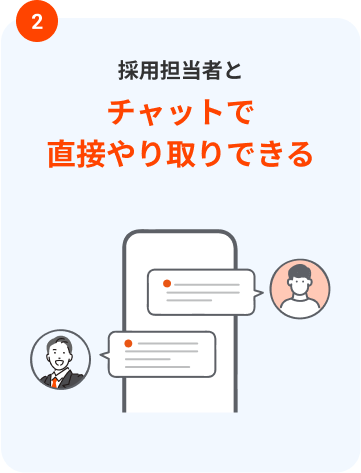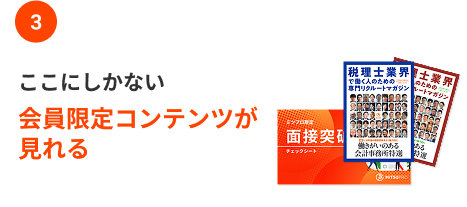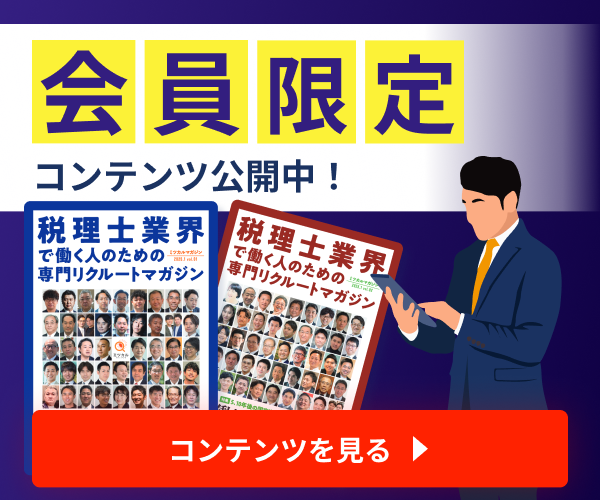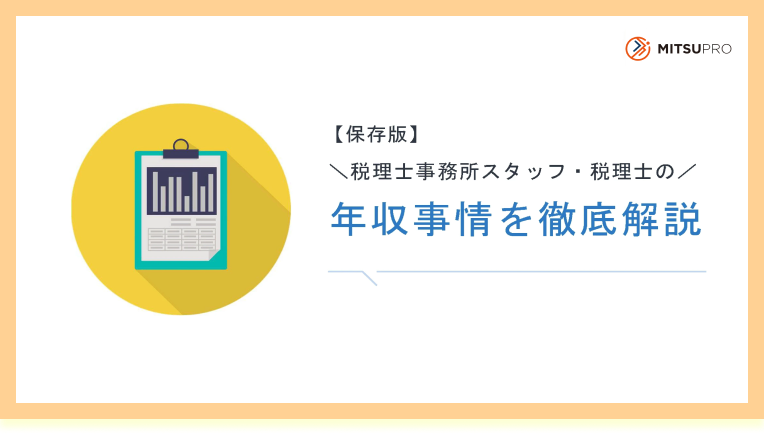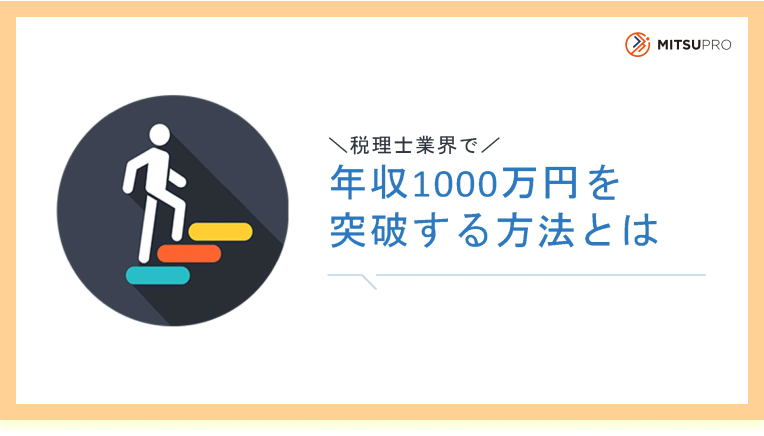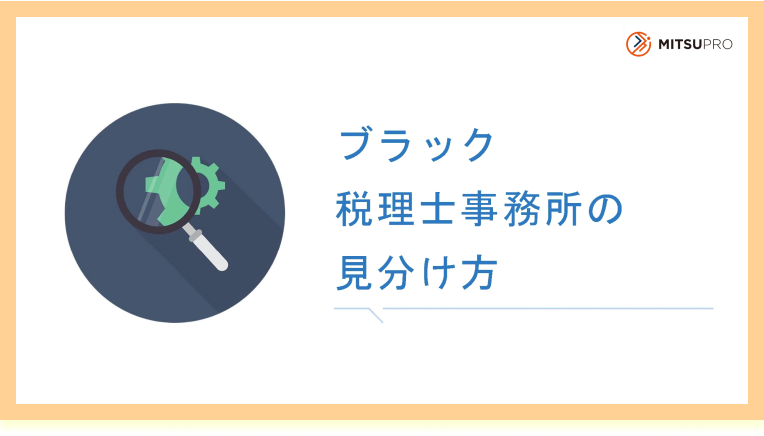INDEX
おすすめ記事
-
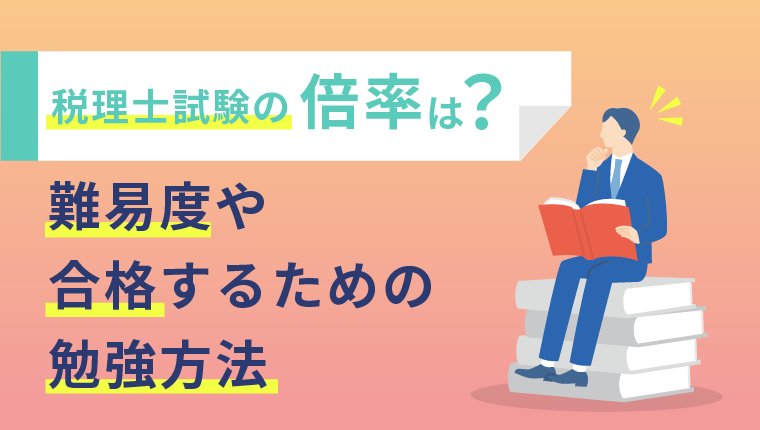
税理士試験の倍率は?難易度や合格するための勉強方法
-
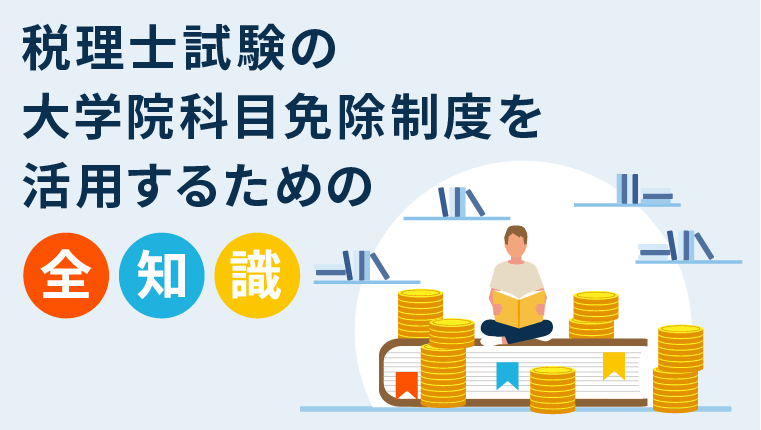
税理士試験の大学院科目免除制度を活用するための全知識
-

税理士試験の住民税をマスターするための対策ガイド|税理士試験対策
-
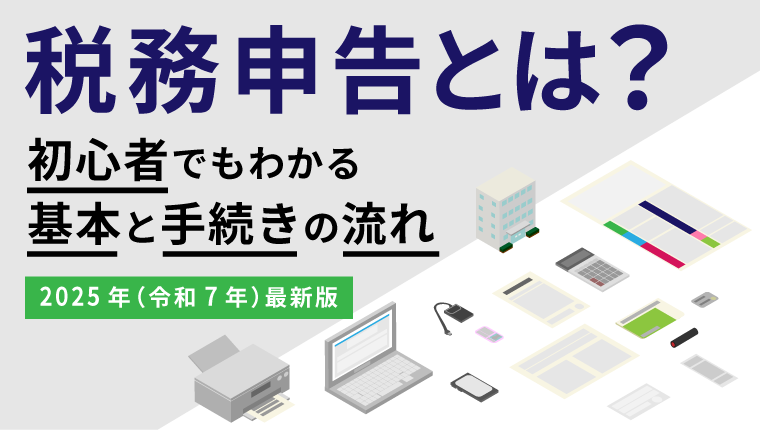
税務申告とは?初心者でもわかる基本と手続きの流れ【2025年(令和7年)最新版】
-
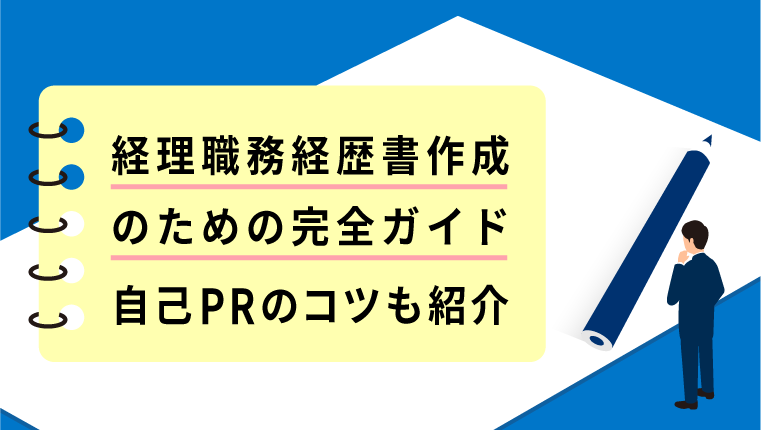
経理職務経歴書作成のための完全ガイド:自己PRのコツも紹介
【2026年版】税理士試験簿記論の全貌|出題傾向と合格へのロードマップ


公開日:2025/08/21
最終更新日:2025/08/21
INDEX
税理士試験の最初の関門ともいえるのが「簿記論」です。税理士試験の必須科目であり、すべての基礎となる分野であるため、多くの受験生が最初に挑戦します。しかし「計算量が多い」「時間が足りない」「合格基準が見えにくい」といった声が絶えず、難関科目として知られています。
本記事では、2026年版の最新情報を踏まえて、簿記論の試験概要から出題傾向、効率的な勉強法、合格までのロードマップを徹底解説します。これから受験を検討している方や、学習に不安を感じている方にとって、最短で合格へ近づける指針となるはずです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
1. 税理士試験「簿記論」とは?
1-1. 簿記論の位置づけ
簿記論は、税理士試験の必須科目のひとつです。もう一つの必須科目である「財務諸表論」とセットで受験する必要があり、税理士を目指すすべての人が避けて通れない登竜門といえます。
その役割は単なる暗記科目ではなく、会計学全体の基礎を固めることにあります。簿記論で学ぶ商業簿記や工業簿記の知識は、法人税法・所得税法・相続税法など、他の応用科目を理解するうえで欠かせません。実際、簿記論をしっかりと学習しているかどうかが、後の科目での成績に大きく影響するケースも少なくありません。
さらに、簿記論は実務にも直結するスキルです。会計処理を正確かつスピーディーに行う力は、税理士業務の根幹。顧問先の月次処理や決算業務をこなす上でも、この科目で培った知識と処理能力が大きく役立ちます。つまり、簿記論は「試験に受かるための科目」という枠を超えて、実務力を磨くトレーニングの場ともいえるのです。
1-2. 試験概要(2026年度版)
簿記論の試験は、試験時間が2時間で、記述式の形式を採用しています。選択肢から答えを選ぶマークシート形式ではなく、答案用紙に直接仕訳や計算過程を書き込む方式であり、正確さとスピードが同時に求められます。
出題範囲は非常に広く、商業簿記の全般がカバーされます。具体的には、連結会計・本支店会計・税効果会計・リース会計といった商業簿記の応用分野まで幅広く出題されるのが特徴です。
合格基準は一般的に「満点の60%前後」とされていますが、実際には絶対評価ではなく、相対評価の要素が強いのが実情です。つまり、問題が易しければ合格ラインは高くなり、難しければ低くなるという仕組みです。難易度によって合格点が調整されるため、毎年「何点取れば合格できるのか」が明確にわからない科目ともいえます。
1-3. 合格率の目安
簿記論の合格率は、例年 10〜15%前後 にとどまっています。これは税理士試験全体の中でも決して高い数字ではなく、受験生にとって大きな壁となっています。
さらに年度によっては難問が連続して出題されることもあり、その場合は合格率が5%台まで落ち込むこともあります。つまり、年によって試験の難易度が大きく変わるため、安定した合格率が期待できないのです。
このため簿記論は、単に「合格点に到達する」ことを目指すのではなく、受験生全体の中で上位20%に入ることを意識する科目といえます。上位層に食い込むためには、難問への対応力よりも「基礎論点を確実に正答する力」が求められます。合格を勝ち取るためには、日頃から凡ミスを減らし、計算精度を高める学習が不可欠です。
2. 簿記論の出題傾向(過去5年の分析)
簿記論は「商業簿記」と「工業簿記」の両方から幅広く出題されます。過去5年の試験を分析すると、頻出分野とそうでない分野がはっきりと分かれます。ここでは主要テーマを整理し、学習の優先順位を明確にしていきましょう。
2-1. 商業簿記の傾向
商業簿記は、毎年必ず大きな配点が与えられる分野です。特に「連結会計」や「決算整理仕訳」は鉄板テーマであり、対策を怠ることはできません。
| テーマ | 出題頻度 | ポイント |
| 連結会計 | 毎年高頻度 | 子会社・関連会社の処理。部分点を確実に拾うための基礎理解が重要。 |
| 本支店会計・組織再編 | 減少傾向 | 出題は減っているが、基本論点として押さえる必要あり。 |
| 決算整理仕訳 | 毎年必出 | 減価償却・引当金・棚卸資産評価など。スピードと正確性が鍵。 |
| 税効果会計・リース会計 | 出題増加 | 難解論点だが、応用力を問う問題として頻出化している。 |
解説
・連結会計は「ほぼ毎年出題」の最重要テーマ。仕訳や精算表の作成に加え、個別財務諸表との調整を素早く行う力が求められます。
・本支店会計・組織再編は出題頻度が下がっていますが、基本論点を落とすと大きな失点につながるため軽視は禁物です。
・決算整理仕訳は、どの年度でも必ず登場する「落とせない問題」。短時間で正確に処理できるまで演習を重ねることが重要です。
・税効果会計やリース会計は難易度が高いですが、近年は毎年のように出題されるため対策必須。応用論点をどこまで拾えるかが合否を分けます。
2-2. 計算問題の特徴
簿記論の最大の特徴は、膨大な計算量と1問ごとの配点の重さにあります。
| 特徴 | 内容 | 学習上の注意点 |
| 膨大な計算量 | 仕訳、勘定記入、財務諸表作成まで幅広く問われる | 手を止めずに計算し続ける集中力が必要 |
| 配点の大きさ | 1問の分量が多く、途中で崩れると大失点 | 部分点を狙える答案作成力を磨く |
| 理論問題 | 出題頻度は少ないが「計算根拠を説明せよ」という形式で出題される | 計算と理論をつなげて理解する姿勢が必要 |
解説
・試験では、全問を解き切るのはほぼ不可能です。そのため「取るべき問題」と「捨てる問題」を事前に決めておく戦略が欠かせません。
・特に仕訳や勘定記入はケアレスミスが致命傷になるため、基礎問題こそ慎重に正答することが重要です。
・理論問題は少ないものの、計算の背景を問う形式で登場することがあるため、単なる丸暗記ではなく「なぜその処理を行うのか」を説明できる理解が求められます。
3. 簿記論の難易度と受験生が感じる壁
簿記論は「量が多く時間が足りない」「凡ミスが命取り」「合格点が相対的に変動する」という3つの大きな壁が存在します。これらを理解し、あらかじめ対策を練ることが合格への近道となります。
3-1. 時間との戦い
簿記論の試験時間は2時間ですが、出題量は非常に多く、すべての問題を解き切ることはほぼ不可能です。そのため、最初から「全部を解こう」とするのではなく、得点効率の高い問題に集中し、難問は潔く捨てるといった取捨選択の判断力が求められます。時間配分の戦略を持たないまま試験に挑むと、途中で時間切れとなり、大きな失点につながります。
3-2. ケアレスミスの多発
簿記論は「凡ミス即失点」の試験です。計算や仕訳の量が多いため、数字の転記ミスや桁数の誤りが合否を分けることも珍しくありません。難しい応用問題に挑むよりも、基礎的な問題を確実に正答することが合格へのカギです。特に、決算整理仕訳や原価計算の基礎問題を取りこぼさない姿勢が重要になります。
3-3. 相対評価の怖さ
簿記論は絶対評価ではなく、実際には相対評価に近い仕組みで合否が決まります。例えば、60点を超えても合格できない場合がある一方で、問題が難しかった年には50点台で合格するケースもあります。つまり、他の受験生に勝ち抜く意識が必要であり、自分だけの得点目標を固定するのではなく、相対的に上位2割に入ることを意識することが大切です。
4. 合格へのロードマップ
簿記論は一夜漬けで合格できる科目ではなく、計画的に学習時間を確保することが必須です。合格者の多くは半年から1年かけて、段階的に力を積み上げています。
4-1. 学習時間の目安
簿記論の学習時間は、受験生のバックグラウンドによって大きく異なります。初めて簿記に触れる人と、すでに日商簿記2級を取得している人では必要な勉強時間に差があるのが一般的です。
・初学者の場合:800〜1,000時間程度
会計や簿記の基礎知識がゼロのため、テキスト理解から始める必要があります。基礎を固めるまでに時間がかかるため、1年程度の学習期間を見込むのが安全です。
・簿記2級保持者の場合:500〜700時間程度
仕訳や決算の基礎は身についているため、簿記論特有の応用分野や大量演習に重点を置けば半年ほどで合格レベルに到達可能です。
いずれの場合も、「毎日の学習時間 × 継続性」が合否を分けます。週末にまとめて勉強するよりも、1日1〜2時間でもコツコツ継続するほうが効果的です。
4-2. 学習ステップ
簿記論の学習は「基礎 → 応用 → 実戦力 → 直前期の総仕上げ」という流れで進めるのが王道です。段階ごとに目的を明確にし、学習内容を整理すると効率的に合格に近づけます。
| 学習ステップ | 期間の目安 | 学習内容 | 目的 |
| ステップ1:基礎固め | 3〜4か月 | テキスト+問題集で「仕訳 → 勘定 → 財務諸表」の流れを理解。商簿・工簿ともに基礎論点を徹底反復 | 知識の定着と基礎力の養成 |
| ステップ2:応用力養成 | 2〜3か月 | 過去問演習で出題形式に慣れる。連結会計・原価計算など頻出テーマを重点的に対策 | 出題傾向の把握と応用力の強化 |
| ステップ3:答案練習・模試 | 2か月 | 2時間で問題を解く練習を繰り返す。ケアレスミスを防ぐチェックリストを作成 | 実戦力と時間配分の習得 |
| ステップ4:直前期 | 1か月 | 予備校答練・模試で仕上げ。「捨て問」を事前に決め、解答順序と時間戦略を最適化 | 本試験で安定得点を狙う準備 |
5. 簿記論の効果的な勉強法
簿記論は「知識の暗記」よりも「手を動かす演習量」がものをいう科目です。合格者の多くは、テキストを何度も読み込むよりも、過去問演習・答案練習を中心とした学習スタイルを採用しています。ここでは、特に効果的とされる勉強法を4つに整理します。
5-1. 過去問中心の学習
簿記論の出題は毎年形式が似ており、過去問を徹底的にやり込むことが最短ルートです。最低でも過去10年分を3周は解きたいところです。
・出題パターンに慣れる
・問題文のボリューム感を体感する
・部分点が狙える答案作成の練習になる
5-2. 問題演習の徹底
簿記論は「インプット:アウトプット=3:7」が理想的。テキストを理解したら、すぐに問題演習で手を動かしましょう。
・1問解いたら必ず振り返り、解法のプロセスを確認
・間違えた問題は「解けなかった理由」をノート化
・問題集を1冊「穴がない状態」に仕上げることが目標
5-3. スピード強化の工夫
時間不足に泣く受験生が多いため、普段から「速く解く」訓練が欠かせません。
・電卓の指使いを固定して無駄な動きをなくす
・仕訳を素早く書く練習をする(省略記号を工夫する)
・問題集を「時間制限付き」で解く習慣を持つ
5-4. 模試の活用法
模試は本試験を疑似体験できる絶好の機会です。点数そのものよりも「時間配分」や「ミスの傾向」を分析する材料にしましょう。
・実戦さながらに2時間で解く練習
・得点よりも「どこで時間を使いすぎたか」を分析
・模試後の復習で「解けなかった問題」を重点的に潰す
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士試験の簿記論は、合格率10〜15%の難関ですが、出題傾向はある程度予測可能であり、適切な学習戦略を立てれば突破は十分可能です。
簿記論は「努力の量と方向性」が合否を決める科目です。正しいロードマップに沿って学習を進めれば、2026年合格は決して夢ではありません。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)