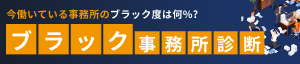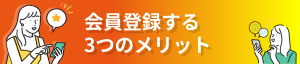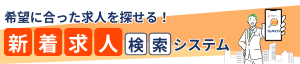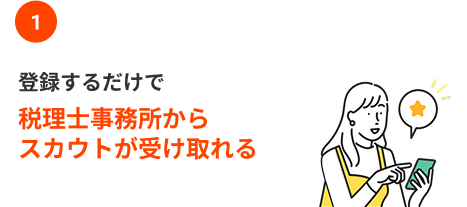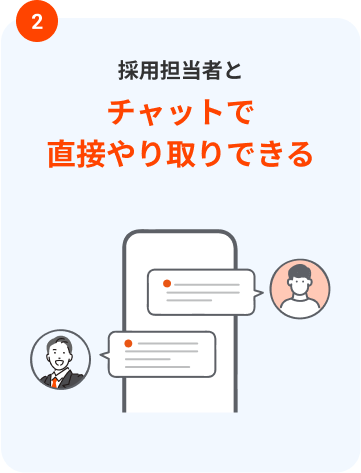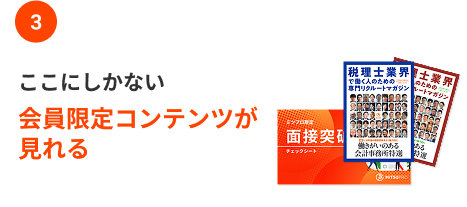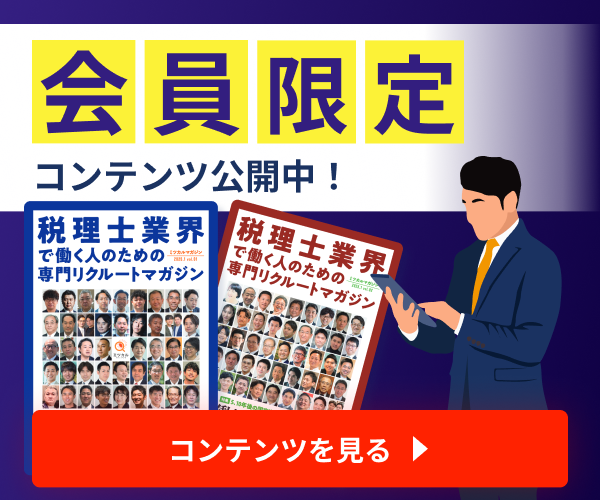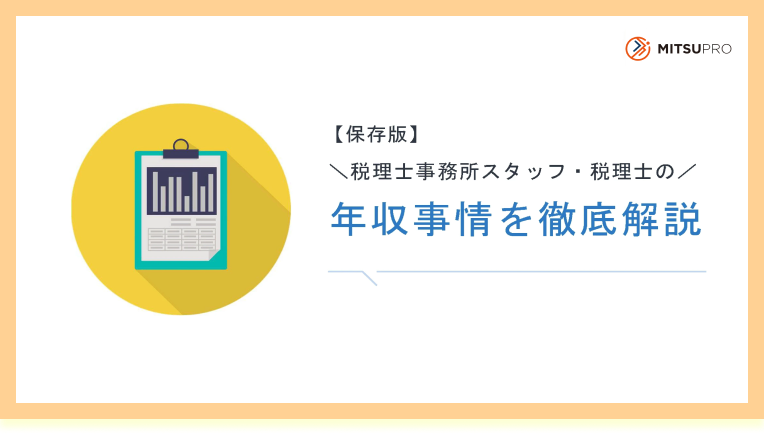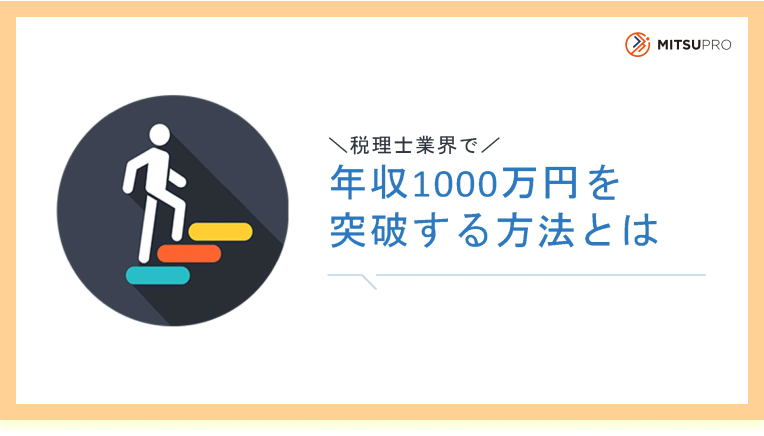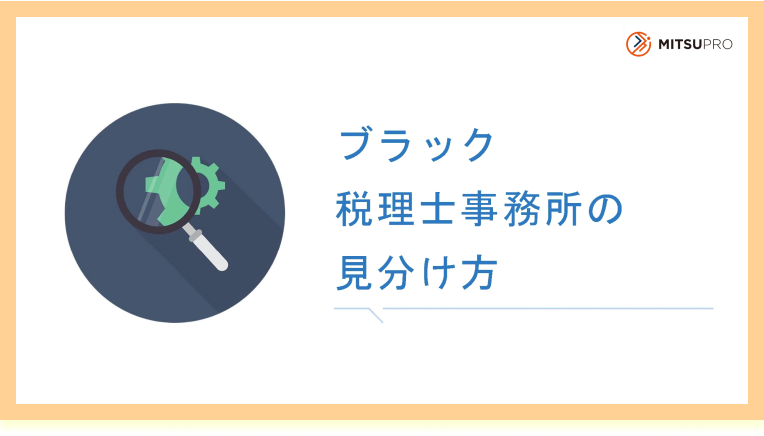INDEX
おすすめ記事
-
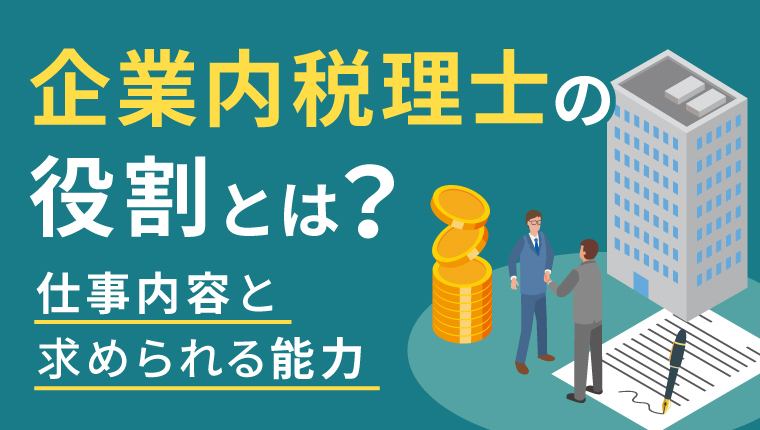
企業内税理士の役割とは?仕事内容と求められる能力
-

女性が税理士になるメリットとは?働き方から年収まで徹底解説!
-

還付申告の準備と手続き【2025年最新版】
-

トランプ関税で日本企業はどうなる?税理士が知っておきたい貿易リスクの新常識
-

簿財の最新情報【2025年最新版】:試験の難易度やキャリアパスを徹底分析
財務諸表論の難易度・合格率・勉強時間を徹底解説【税理士試験】


公開日:2025/08/07
最終更新日:2025/08/07
INDEX
税理士試験の主要科目のひとつである「財務諸表論」。名前は聞いたことがあるけれど、内容が難しそうでとっつきにくいと感じている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、財務諸表論の基礎的な内容から、試験対策、効率的な勉強方法まで、初心者の方でも理解できるように丁寧に解説していきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
財務諸表論とは?
財務諸表論は、企業の会計情報を正確に作成・分析・報告するための理論と実務を学ぶ科目です。
もう少しかみ砕くと、企業が作成する「財務諸表」(損益計算書や貸借対照表など)の理論的な根拠と、実際にそれらを作成するための計算実務の両方を問われる試験です。
財務諸表って何?
財務諸表とは、会社の「成績表」ともいえる書類のことで、主なものは以下の通りです。
| 財務諸表の種類 | 概要 |
| 損益計算書(P/L) | 会社の1年間の儲けを表す |
| 貸借対照表(B/S) | 会社の財産状況を表す |
| キャッシュフロー計算書 | 現金の動きを表す |
| 株主資本等変動計算書 | 資本の変動状況を表す |
これらの書類がどうやって作られているのか、その根拠は何か、を学ぶのが「財務諸表論」です。
財務諸表論はどんな試験?
税理士試験の財務諸表論は、理論問題と計算問題の両方が出題されるのが特徴です。
試験概要(令和7年度時点)
| 項目 | 内容 |
| 試験時間 | 2時間 |
| 満点 | 100点(計算50点、理論50点) |
| 合格ライン | 概ね60点前後(相対評価) |
| 出題形式 | 記述式(マークシートではない) |
| 合格率 | およそ10〜15%程度 |
理論と計算、どちらもバランスよく得点することが重要です。
財務諸表論の学習内容
財務諸表論の学習内容は、大きく分けると、「理論」と「計算」の2本柱です。
理論分野の学習内容
理論では、「会計基準」や「企業会計原則」など、財務諸表を作成する際の考え方を学びます。
主なトピックは以下の通りです。
・企業会計原則
・会計基準(収益認識、リース、金融商品など)
・財務諸表の意義と役割
・会計上の見積りと表示の方法
暗記だけでなく、論理的な理解が求められます。
計算分野の学習内容
計算では、実際に財務諸表を作成するための数値計算を行います。
具体的な内容は以下の通りです。
・精算表の作成
・減価償却の計算
・引当金・棚卸資産の評価
・株式発行・自己株式の処理
・税効果会計や連結会計の基礎
簿記論との違いは?
税理士試験において、「財務諸表論」と「簿記論」はセットで受験されることが多い科目です。両者は一見似ているように思われがちですが、目的や出題内容に明確な違いがあります。
財務諸表論と簿記論の比較表
| 項目 | 財務諸表論 | 簿記論 |
| 主な出題内容 | 理論+計算 | 計算のみ |
| 計算の傾向 | 表示・開示寄り(財務諸表の作成) | 記帳寄り(仕訳・帳簿) |
| 理論の有無 | あり(会計基準・企業会計原則など) | なし(理論問題は出題されない) |
| 問題形式 | 記述式(文章・計算) | 記述式(計算中心) |
| 難易度の傾向 | バランス重視(理論・計算ともに配点あり) | 計算特化で正確性とスピードが要求される |
それぞれの科目が向いている人
・財務諸表論が向いている人: 論理的な文章を書くのが得意な人、会計の背景や理屈を理解したい人
・簿記論が向いている人: 計算が得意な人、反復練習で精度を高められる人
どちらを先に勉強すべき?
初学者には同時並行の学習がおすすめです。計算分野では重複する部分も多く、相乗効果が期待できます。
ただし、どうしても1科目から始める場合は、「計算に慣れる」目的で簿記論からスタートするのも一案です。
財務諸表論の難易度
財務諸表論の合格率は毎年10〜15%前後と、決して高くありません。ただし、ポイントを押さえた対策をすれば十分合格可能です。
財務諸表論の合格率
財務諸表論の合格率は以下の様に推移しています。
他の教科に比べ、合格率の変動が大きいことが特徴です。
| 年度(回数) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 備考 |
| 令和6年(第74回) | 13,665 | 1,099 | 8.0% | 近年で最も低い合格率 |
| 令和5年(第73回) | 13,251 | 3,722 | 28.1% | 前年から大幅上昇 |
| 令和4年(第72回) | 10,118 | 1,502 | 14.8% | 前年から大幅下落 |
| 令和3年(第71回) | 8,568 | 1,630 | 19.0% | - |
| 令和2年(第70回) | 8,568 | 2,045 | 23.9% | コロナ禍での試験実施 |
| 令和元年(第69回) | 9,268 | 1,753 | 18.9% | - |
| 平成30年(第68回) | 8,817 | 1,183 | 13.4% | 前年から大幅下落 |
| 平成29年(第67回) | 10,424 | 3,087 | 29.6% | 近年で最も高い合格率 |
| 平成28年(第66回) | 11,420 | 1,749 | 15.3% | - |
| 平成27年(第65回) | 12,202 | 1,901 | 15.6% | - |
| 平成26年(第64回) | 11,663 | 2,148 | 18.4% | - |
財務諸表論の難易度
また、財務諸表論の難易度は以下の様になっています。
① 理論:暗記量が多く、文章表現力も必要
理論問題では、「企業会計原則」や「会計基準」などに関する記述式の問題が出題されます。単に丸暗記するのではなく、理論の背景や考え方を理解した上で、論理的に説明する力が求められます。
② 計算:一つのミスが致命傷、応用力も必須
計算問題では、仕訳・精算表・財務諸表作成などの会計処理の正確性が問われます。単純な計算力だけではなく、論点の組み合わせに対応する応用力が必要です。
③ 試験時間:2時間で理論と計算を解き切る“時間管理力”が鍵
財務諸表論の試験時間は2時間。理論問題(2題)と計算問題(1題)を1セットで解く必要があります。この時間配分が難しく、得点力より先に“時間切れ”で失点する受験生も少なくありません。
合格に必要な勉強時間
財務諸表論の合格に必要な勉強時間は、一般的に500〜600時間程度といわれています。ただし、これはあくまで目安であり、個人の前提知識や学習環境によって変動します。
以下では、受験生のタイプ別に必要な時間やスケジュール感を詳しく見ていきます。
① 初学者(会計の知識ゼロからスタート)
| 状況 | 必要学習時間 | 学習期間の目安 |
| 会計未経験者 | 600〜700時間 | 6〜8ヶ月 |
| 他資格なし/初受験 | 基礎インプットに時間がかかる |
・理論の文章表現にも慣れが必要
・通信講座や予備校のサポートを活用すると効率UP
② 簿記2級・3級保有者
| 状況 | 必要学習時間 | 学習期間の目安 |
| 簿記2級レベル | 約500〜600時間 | 5〜6ヶ月 |
| 基礎がある分、計算の習得は比較的スムーズ |
・理論の対策に重点を置けるのがメリット
③ 簿記1級保有者/実務経験者
| 状況 | 必要学習時間 | 学習期間の目安 |
| 会計実務・簿記1級 | 約400〜500時間 | 3〜4ヶ月 |
| 基本的な会計処理に自信がある方向け |
・理論対策に時間を集中できるため、短期合格も狙える
勉強時間を確保するには?
| 勉強期間 | 目標時間 | 必要な1日の勉強時間 |
| 6ヶ月 | 約540時間 | 約3時間/日 |
| 4ヶ月 | 約500時間 | 約4〜4.5時間/日 |
| 3ヶ月 | 約450時間 | 約5時間/日 |
※ 土日や祝日を「多めに勉強する日」として設定すると、平日は1.5〜2時間でも調整可能です。
財務諸表論の勉強法【初心者向け】
ここからは、初学者の方に向けて、具体的な学習ステップを紹介します。
ステップ①:全体像をつかむ
まずは教科書や講義を通じて、どんな内容があるのかをざっくり理解しましょう。
・理論と計算のバランスを知る
・会計の目的をイメージする
・「なぜこの処理が必要なのか?」を意識する
ステップ②:インプット学習(基礎固め)
基本テキストや講義動画で基礎を徹底的にインプットします。計算も理論も、最初から完璧を目指す必要はありません。
・計算問題は1つずつステップを確認
・理論はまず「流れ」と「用語」を理解
ステップ③:アウトプット学習(演習)
インプットが終わったら、過去問や答練(模擬問題)でアウトプット中心の学習に切り替えます。
・理論:過去問を繰り返し書いて覚える
・計算:仕訳・精算表・B/S・P/L作成の流れをマスター
・解き直しノートを作ると◎
直前期は記述力を強化
本番では「書いて伝える力」が必須です。理論では文章の構成やキーワードの使い方が得点に直結します。
・書き慣れる
・予備校の模範答案を参考にする
・要点を意識して簡潔にまとめる
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
財務諸表論は、会計の本質を問う非常に奥深い科目です。数字を扱うだけでなく、その背後にある考え方や企業の意思決定にまで踏み込むことで、実務にも直結する力が身につきます。
初学者にとっては、最初はとっつきにくいかもしれませんが、地道に学習を積み重ねれば、確実に理解が進みます。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)