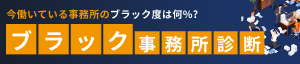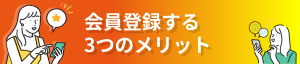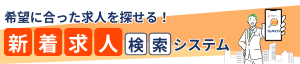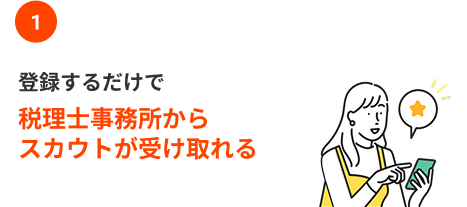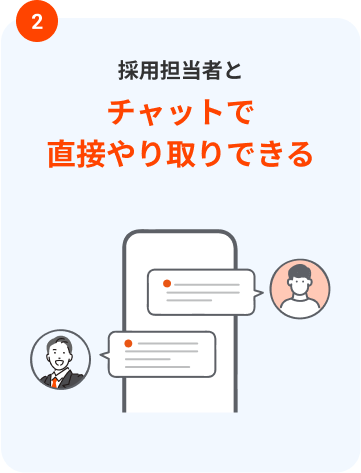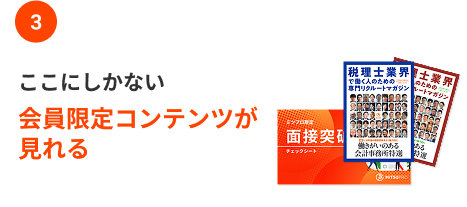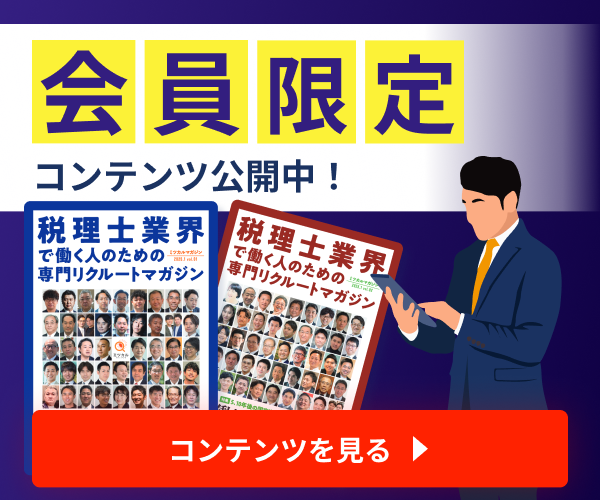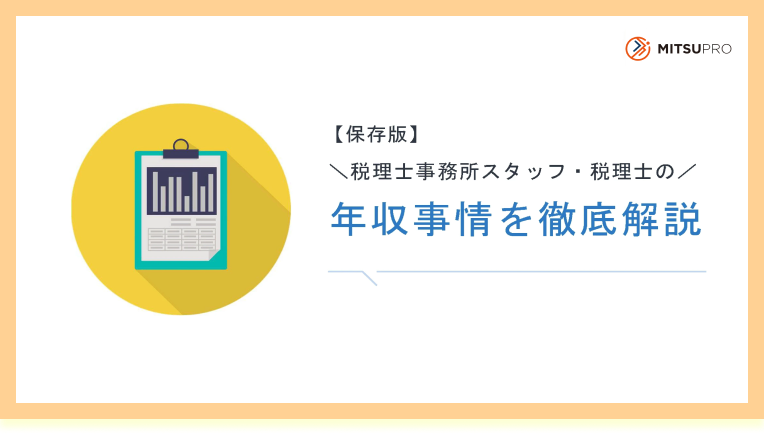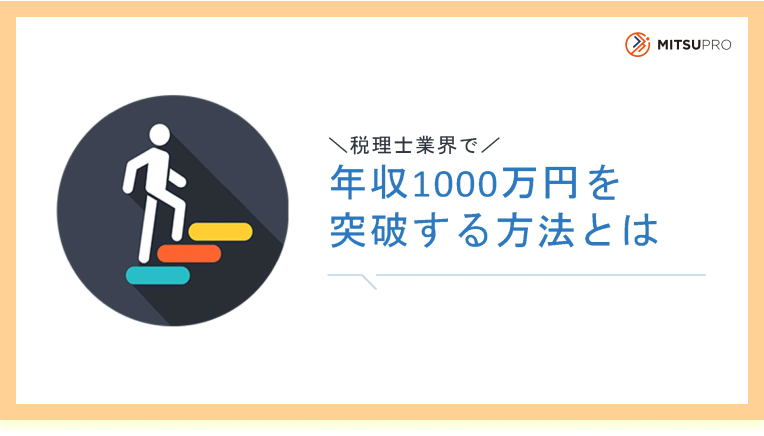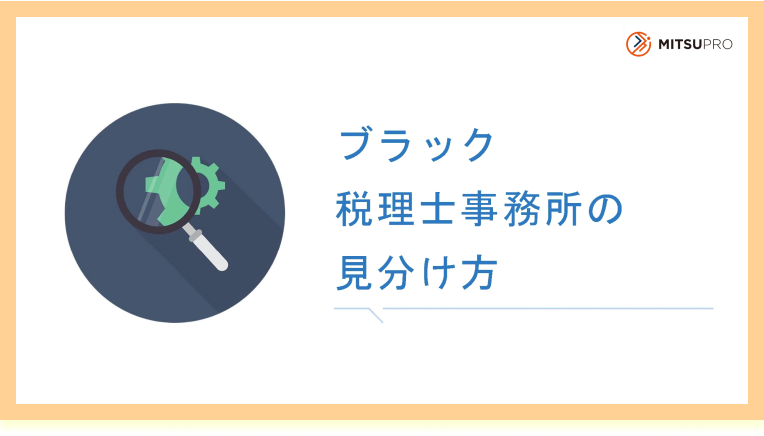INDEX
おすすめ記事
-
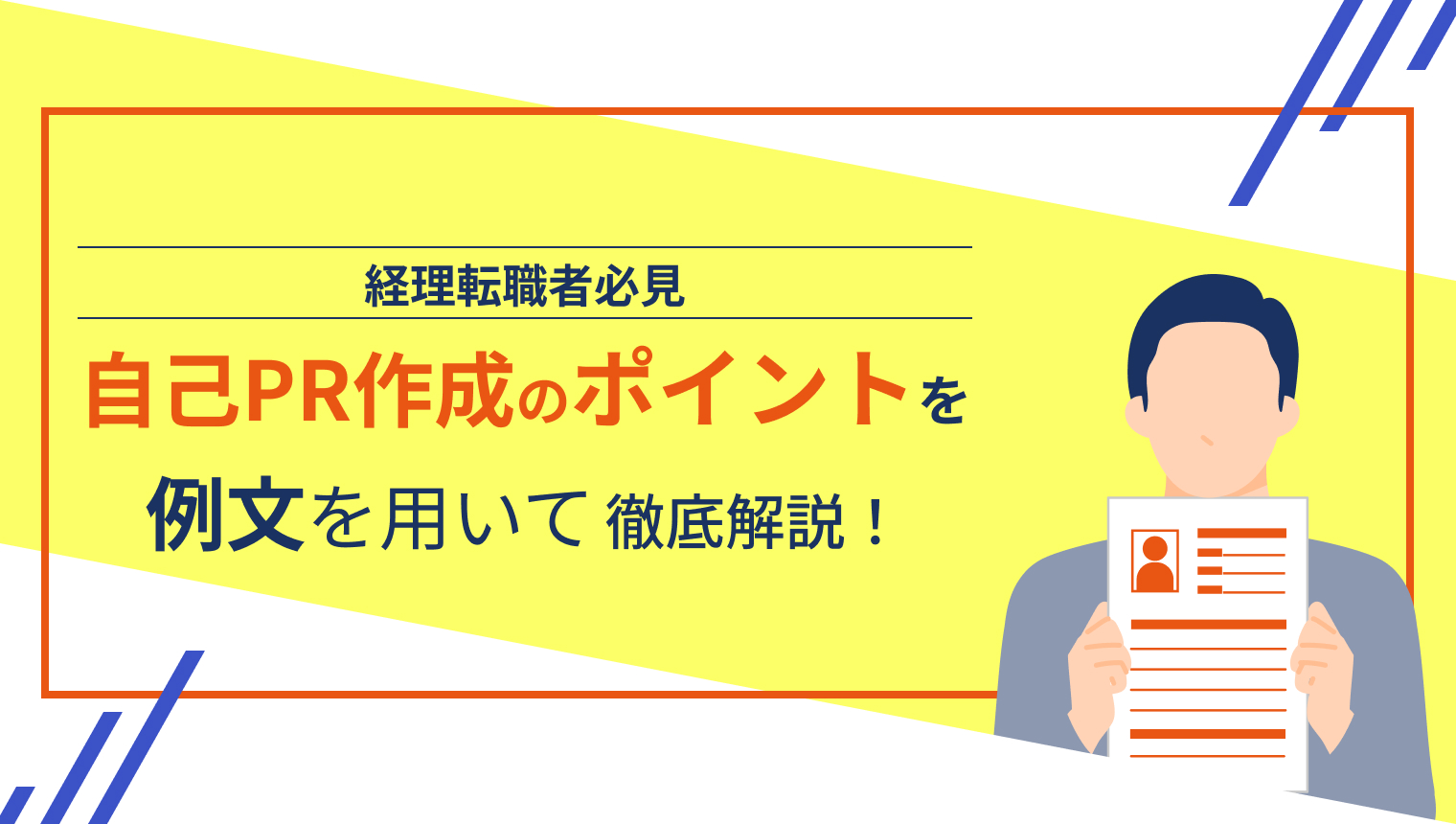
【経理転職者必見】自己PR作成のポイントを例文を用いて徹底解説!
-
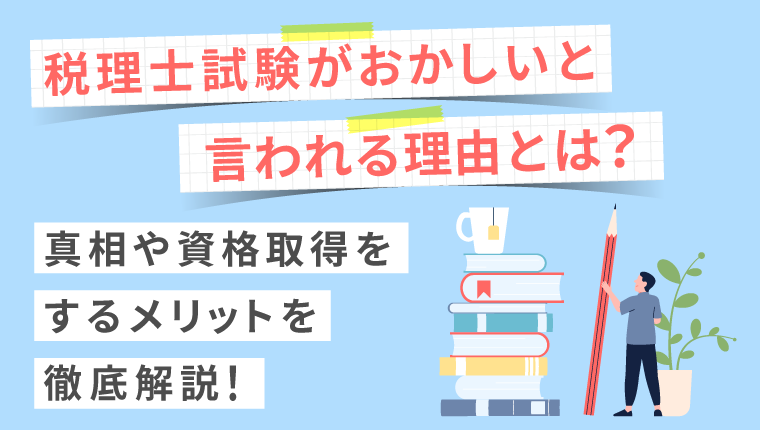
税理士試験がおかしいと言われる理由とは?真相や資格取得をするメリットを徹底解説!
-
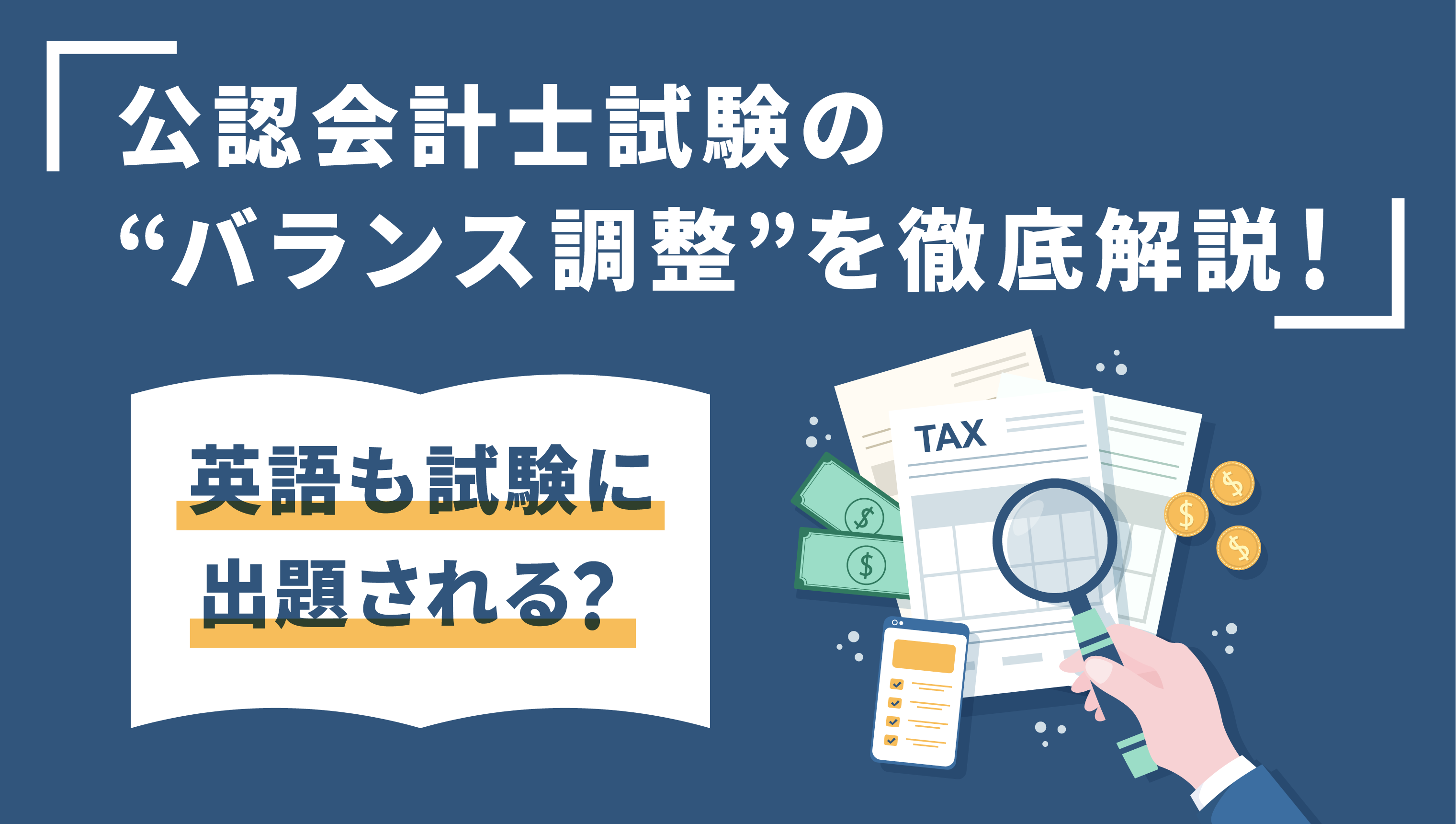
公認会計士試験の“バランス調整”を徹底解説!英語も試験に出題される?
-
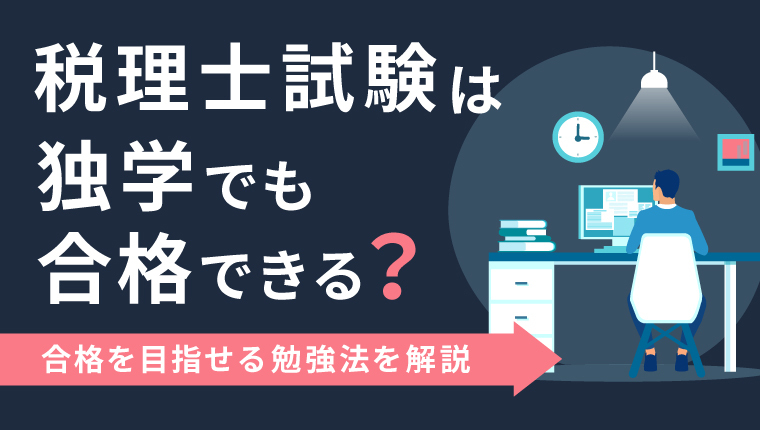
税理士試験は独学でも合格できる?合格を目指せる勉強法を解説!
-
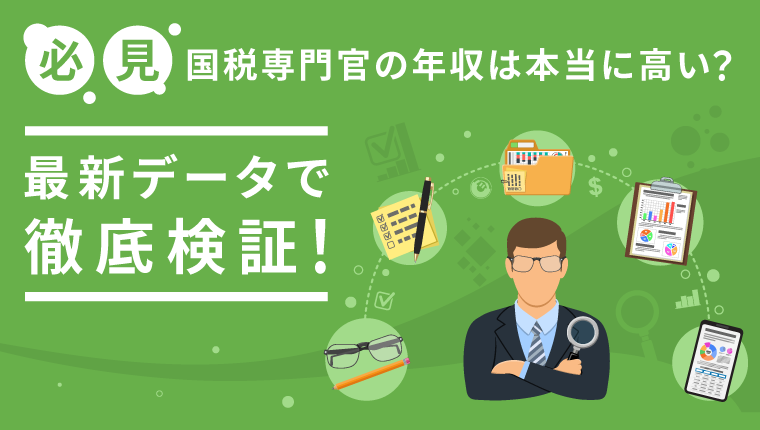
【必見】国税専門官の年収は本当に高い?最新データで徹底検証!
「戦略分野国内生産促進税制」とは?制度概要と申請の留意点を徹底解説


公開日:2025/06/16
最終更新日:2025/08/16

INDEX
2024年度税制改正で創設された「戦略分野国内生産促進税制」は、企業の戦略的投資を支援する新たなインセンティブです。特にGX(グリーントランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)、経済安全保障といった分野での生産投資を促進するため、設備投資ではなく生産・販売量に応じた税額控除を実現した制度として注目されています。
本記事では、税理士として押さえておくべき制度の背景、対象分野、税額控除の内容、適用条件、申請実務上の留意点まで、体系的に解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
制度創設の背景
国際的な産業政策競争の激化
米国のインフレ抑制法(IRA法)やCHIPS法、欧州のグリーンディール産業計画など、主要国が戦略分野への集中投資を推進する中、日本も対抗措置として本制度を創設しました。特にGX(グリーントランスフォーメーション)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、経済安全保障という3つの戦略分野において、民間投資の促進が急務となっています。
従来制度との根本的相違点
本制度の最大の特徴は、設備投資額ではなく「生産・販売量」を基準とした税額控除を行う点です。対象分野は初期投資よりも生産段階でのコストが高く、従来の設備投資促進税制では十分な効果が得られにくい特性があります。生産段階での直接的な支援により、継続的な国内生産へのインセンティブを提供する仕組みとなっています。
財源としてのGX経済移行債
政府は20兆円規模のGX経済移行債を10年間で発行し、その一部を本制度の財源として活用します。官民合わせて150兆円規模のGX関連投資創出を目標とする大規模な産業政策の一環として位置づけられています。
対象となる5つの戦略分野
本税制の対象は、国際競争が特に激しく、日本にとって戦略的重要性の高い次の5分野に限定されています。
電気自動車等分野
対象車両は電気自動車(EV)、軽自動車の電気自動車(軽EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)に限定されます。重要な点として、通常のハイブリッド自動車(HEV)は対象外であり、完成車のみが対象で蓄電池や個別部品は除外されます。用途による制限はないため、自家用・商用問わず控除対象となります。
グリーンスチール分野
製鉄プロセスの脱炭素化が焦点となります。従来の高炉法(鉄鉱石を石炭で還元)から電炉法等への転換により、CO2排出量を大幅に削減した鉄鋼材料が対象です。製造プロセスの根本的変革を伴うため、技術的・経済的ハードルが高く、政策支援の必要性が高い分野といえます。
グリーンケミカル分野
化学品製造における原料転換が要点です。現在主流のナフサ(石油系原料)から、バイオマス原料や廃プラスチック等の循環資源への転換により製造される化学品が対象となります。原料調達から製造プロセスまでの全面的な見直しが必要な分野です。
持続可能な航空燃料(SAF)分野
航空業界の脱炭素化における重要な要素です。バイオマス由来原料や廃食油等を原料とした航空機燃料が対象で、植物の光合成によるCO2吸収を考慮したカーボンニュートラルな燃料として注目されています。国際航空業界での脱炭素目標達成に不可欠な分野です。
半導体分野
対象はマイコン半導体とパワー半導体を含むアナログ半導体に限定されます。重要な制約として、先端ロジック半導体やメモリ半導体は対象外であり、また初期投資に補助金が交付される計画も除外されます。製造装置や部素材・原料も対象外となっています。
税額控除の仕組みと計算方法
本税制最大の特徴は、生産・販売数量ベースでの税額控除という点にあります。以下のように分野ごとに控除単価が定められています。
| 分野 | 単位あたりの控除額 |
| 電気自動車等 | 1台あたり30万円 |
| グリーンスチール | 1トンあたり1万円 |
| グリーンケミカル | 1トンあたり5万円 |
| SAF | 1リットルあたり30円 |
| 半導体 | 1個あたり府省令で規定 |
この控除額を、生産・販売した数量に掛け合わせた金額が、法人税額から直接控除されます。
投資額上限による制約
控除額には重要な上限があります。各事業年度の控除額は、生産用資産及びこれと共に対象商品を生産するため直接・間接に使用する減価償却資産への投資額合計を超えることができません。この上限は累積ベースで管理され、対象期間全体を通じた累積控除額が累積投資額を上回ることはできない仕組みとなっています。
段階的減額措置
適用期間は最大10年間ですが、8年目以降は控除額が段階的に減額されます。
・8年目:控除額の75%
・9年目:控除額の50%
・10年目:控除額の25%
この措置により、制度開始当初の投資促進効果を重視する設計となっています。
制度適用の要件
適用にあたっては以下の3点が要件となります。
1. 事業適応計画の認定
・経済産業省等の主務大臣による事前認定が必要。
・対象商品の製造能力や国内立地、CO₂削減効果などが審査基準となります。
2. 青色申告法人であること
・青色申告書を提出している法人に限定。
・個人事業主や白色申告法人は対象外。
3. 制度期限内の申請
・令和9年3月31日までに認定申請を行う必要あり。
不適用となるケース
下記すべてを満たす場合、その年度の税額控除は受けられません。
・所得金額が前年度比で増加
・継続雇用者給与等支給総額の増加率が1%未満
・国内設備投資額が当期減価償却費の40%以下
つまり「利益は増えたが、雇用や投資は抑制した」企業には恩恵が与えられない設計となっており、実質的な国内波及効果を重視する制度です。
実務上の申請手続き
この制度を適用するには、「事業適応計画の認定申請」と「法人税申告での税額控除申請」の2段階手続きが必要です。以下、それぞれのフェーズに分けて解説します。
【ステップ1】事業適応計画の認定申請(制度の入口)
1. 電子申請による手続き(経済産業省・対象分野別に)
・経済産業省の専用ポータル(Jグランツ等)を通じて、電子申請します。
・申請対象となる戦略分野(EV、半導体、SAFなど)ごとに申請窓口や申請様式が異なるため、要注意です。
◦申請期限: 令和9年3月31日まで
◦申請方法: 原則としてWEB申請(Gビズフォーム経由)
◦申請先: 事業を所管する主務大臣(複数の省庁にまたがる場合は共同認定)
2. 提出書類(例)
基本申請書類
・事業適応計画の認定申請書(様式第十八)
・添付書面①(表紙など)- Wordファイル
・添付書面②(計算ツールなど)- Excelファイル
戦略分野特有の追加書類
・エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書
・各分野別の事業計画詳細書
3. 認定までの流れ
1.電子申請による提出
2.主務大臣(経済産業省など)による内容審査
3.必要に応じて修正依頼・ヒアリング
4.認定通知の交付(PDF)
※通常、申請から認定まで1~3か月程度かかるとされています。
【ステップ2】設備の取得・生産開始
1. 認定後の対応
・認定後に取得した資産が対象となるため、認定前の着手は控える必要があります。
・生産設備の取得・稼働後、実際に対象製品の生産・販売実績を確定させます。
2. 生産数量の記録
・「いつ・どこで・どれだけ生産したか」という情報を、事業年度ごとに集計し、根拠資料とともに記録保存する必要があります。
例:出荷伝票、在庫記録、製造管理システムのログなど
【ステップ3】法人税申告での税額控除適用]
1. 控除額の算定
・各戦略製品の生産・販売数量 × 単位控除額で税額控除額を算出します。
・ただし、法人税額の40%(半導体は20%)を上限にする必要があります。
2. 法人税申告書への記載
・税額控除に関する明細書(別表六など)に記載。
・必要に応じて「税額控除に関する明細添付書」や「証拠資料一覧表」なども準備。
3. 添付資料の例
| 資料名 | 内容 |
| 認定通知書の写し | 主務大臣からのPDF通知等 |
| 生産数量証明 | 製造管理台帳、出荷記録など |
| 投資資産の取得証明 | 資産台帳、取得契約書、請求書など |
| 控除額計算書 | 生産数量に応じた税額控除の算定根拠 |
【ステップ4】モニタリング・不適用回避
・毎期の所得・給与・投資額をチェックし、不適用要件に該当しないか確認が必要です。
・要件を満たさない年度は控除を受けられないため、事前のモニタリング体制を税理士側で構築することが望ましいです。
他制度との関係性
既存の投資促進税制との併用
本制度はDX投資促進税制やカーボンニュートラル投資促進税制との併用が可能ですが、合算での控除上限が適用されます。複数制度の最適な組み合わせによる税額控除効果の最大化を検討する必要があります。
補助金等との関係
半導体分野では、初期投資に補助金が交付される計画は本制度の対象外となります。国の支援措置の重複排除により、制度間の適切な役割分担が図られています。
税理士としての支援ポイント
税理士の立場から見たとき、本制度活用に向けた支援ポイントは以下の3点です。
① 投資スキーム設計への関与
・設備投資の時点で「どの分野が対象となるか」「控除額がどれだけ見込めるか」といった試算が可能です。
・クライアントの投資意思決定を後押しするうえで、試算資料の作成・提供が鍵となります。
② 事業適応計画の策定支援
・認定申請には、生産能力、雇用効果、環境効果などを記載した計画が必要。
・必要に応じて、行政書士・中小企業診断士など他士業との連携も検討すると効果的です。
③ 継続的モニタリングと税務申告
・適用後も、売上・生産量・雇用・設備投資額など、適用可否に関わる要件をモニタリング。
・不適用リスクが発生しないよう、事前の確認体制が重要です。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
戦略分野国内生産促進税制は、単なる節税策ではなく、国策に沿った事業展開に対して税制が後押しする制度です。補助金との併用も可能であり、計画的な事業設計と税理士の積極的な関与があれば、非常に高い効果を生むことができます。
今後ますます重要性が高まるGX・DX・経済安全保障分野において、顧問先企業の戦略投資を促進する一手として、制度の正確な理解と早期対応が求められます。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)