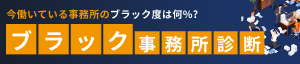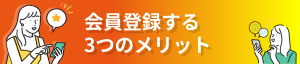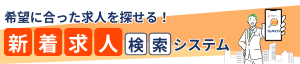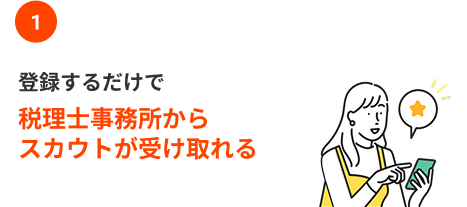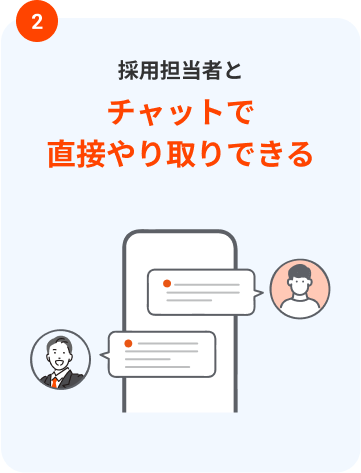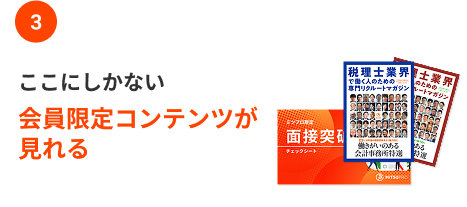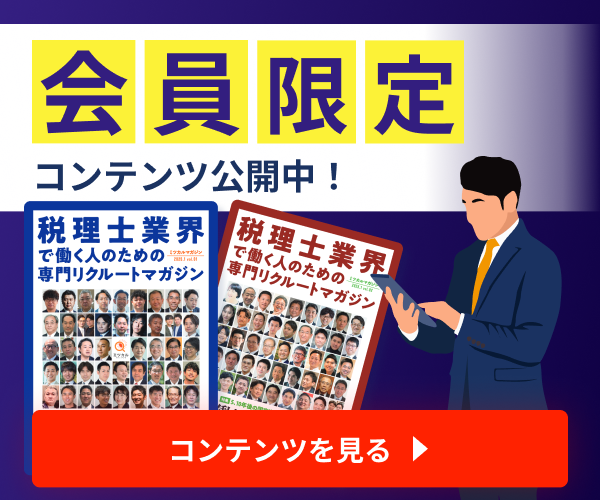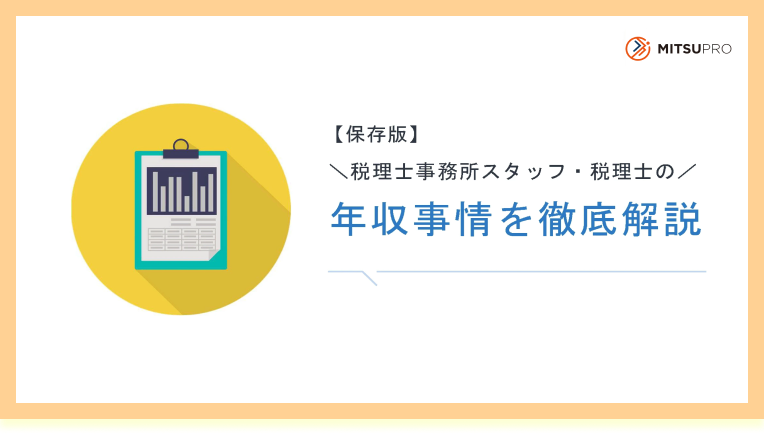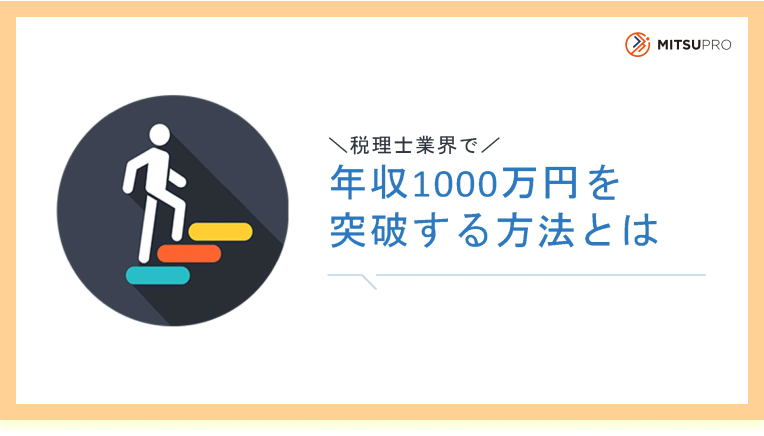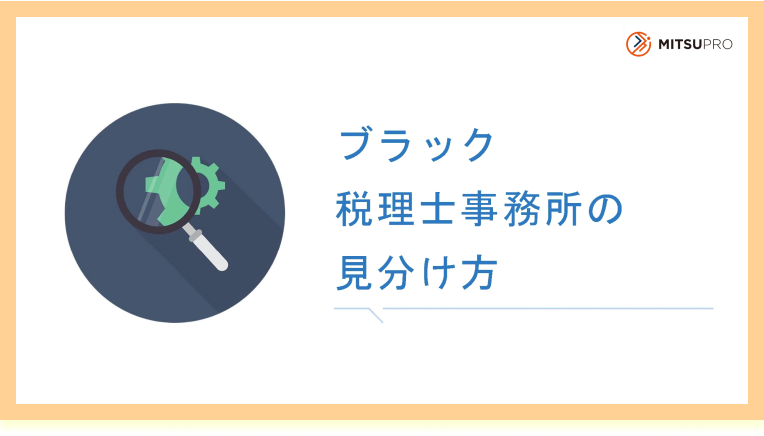INDEX
おすすめ記事
-

税理士法に基づく独占業務とは?税理士以外が行うと違法?
-
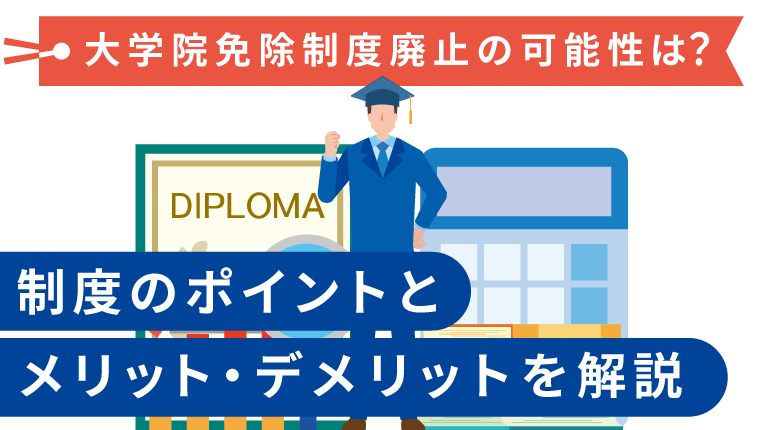
税理士試験の大学院免除制度廃止の可能性は?制度のポイントとメリット・デメリットを解説
-

税理士に向いている人・向いていない人とは?必要なスキルも紹介
-
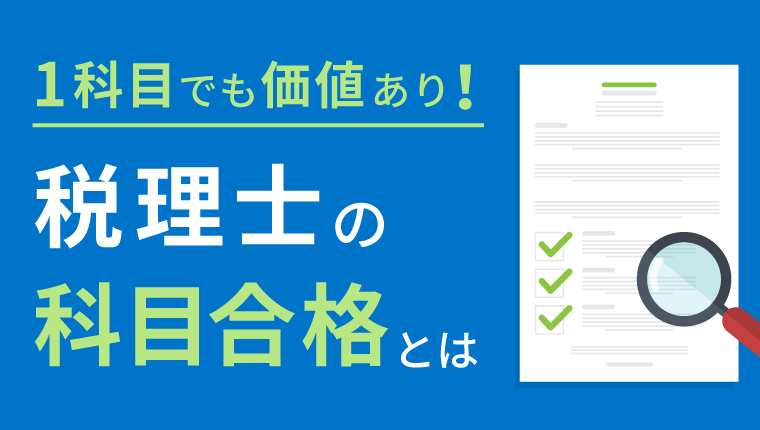
1科目でも価値あり!税理士試験の科目合格とは
-
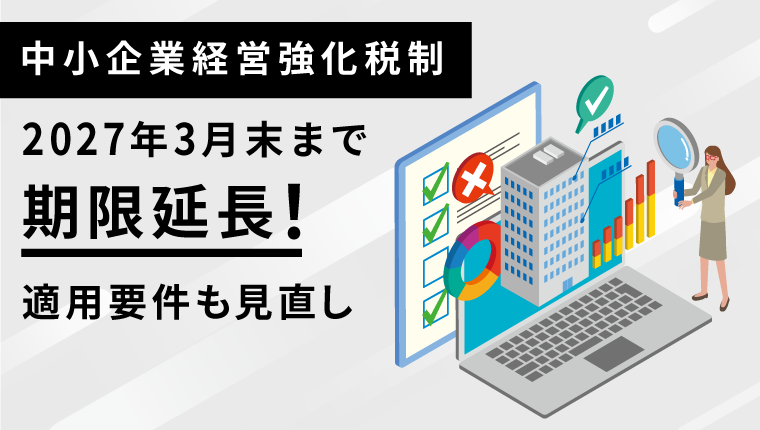
【中小企業経営強化税制】2027年3月末まで期限延長!適用要件も見直し|令和7年度(2025年度)税制改正
公認会計士試験の“バランス調整”を徹底解説!英語も試験に出題される?


公開日:2025/06/16
最終更新日:2025/06/20
INDEX
公認会計士試験は、今まさに大きな転換点を迎えようとしています。近年、試験制度の在り方については、合格者数の増加や試験制度の柔軟性向上など、一定の成果を挙げてきました。しかしその一方で、短答式試験と論文式試験との間で“選抜機能のバランス”が崩れつつあるという課題も指摘されてきました。このバランスの歪みは、試験が本来果たすべき「的確な人材選抜」という目的に対する信頼性を揺るがしかねません。
こうした問題意識のもと、金融庁は2027年度以降を見据えて「公認会計士試験制度のバランス調整」に乗り出しました。本記事では、その背景や調整の具体的な内容、受験生への影響、そして今から何をすべきかについて、最新の動向を踏まえてわかりやすく解説していきます。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
バランス調整が求められる理由
これまでの公認会計士試験制度では、短答式試験における合格率が10%台前半で推移する一方、論文式試験では30%台後半という高い合格率が維持されてきました。つまり、短答で絞り込みすぎた結果、論文の母集団が限定的となり、論述力や応用力を問うべき論文試験の選抜機能が相対的に弱まっているという構造的問題が生じていたのです。
また、短答式試験では、問題数が少なく、一部の問題の得点配分が大きすぎるため、たった1問のミスが合否を左右するなど、受験生にとって非常にストレスフルな形式となっていました。こうした運要素の強い構造では、真に実力のある受験生が不合格になるというリスクが生じ、結果として優秀な人材の流出や受験モチベーションの低下にもつながりかねません。
| 観点 | 現状の課題 | バランス調整が求められる理由 |
| 合格率の乖離 | 短答式:約10%台前半、論文式:約30%台後半 | 試験間で難易度・選抜機能にギャップがあり、不公平感が生じている |
| 短答式の運要素の強さ | 高配点の問題が数問で合否を左右、実力者でも落ちやすい | 実力を正確に測れず、受験生のモチベーションや信頼性に影響する |
| 論文式の通過ハードルの低さ | 思考力や論述力が不十分でも合格可能なケースがある | 会計士としての本来の資質が十分に評価されない恐れがある |
| 母集団の質的偏り | 論文試験に進む受験者の質が十分に担保されていない場合がある | 質の高い合格者を安定的に輩出するためには、入口(短答)の適正化が必要 |
| 将来の実務ニーズとのズレ | 実務では論理的思考力・応用力・新分野(英語・IT等)が必須 | 現行試験では時代に即した能力を測りきれていない |
短答式試験の改善:母集団の拡大と得点構造の見直し
制度改正の柱の一つは、短答式試験の合格者数を段階的に増やすことです。これにより、論文式試験の母集団の多様性を回復させ、実務で活躍できる人材の選抜精度を向上させることが期待されています。合格率を無理に引き上げるのではなく、現行の合格基準(70%)は維持したまま、出題数や配点のバランスを見直すことで、実力に即した合否判定を目指します。
具体的には、財務会計論・管理会計論においては問題数の増加と配点の平準化が予定されており、「1問落とすと不合格」という極端な事態を避ける設計になります。例えば、財務会計論では現状の28問構成を改め、より細分化された出題形式に変更。1問あたりの配点を4〜8点に平準化することで、得点分布のばらつきを抑える狙いがあります。
論文式試験の合格基準を厳格化
もう一つの軸は、論文式試験の合格基準の見直しです。2028年度以降、現在の合格ライン(平均52%)を段階的に引き上げ、最終的には54%まで高める方針が示されています。また、一部科目合格に関しても、従来の「平均点方式」ではなく、「上位15%方式」とすることで、真に高得点を取った受験生に絞り込む方向です。
このような基準引き上げにより、論文式試験が本来持つべき“思考力・表現力・応用力”の評価機能を取り戻し、より高度な専門性を持った人材を選抜することが狙いです。これに伴い、採点体制も強化され、デジタル採点の導入やCBT(Computer Based Testing)の可能性も検討されています。
| 科目 | 現状(2025年まで) | 改正案(2027年〜) |
| 財務会計論 | 200点・120分・28問 | 問数増、配点を4~8点へ平準化 |
| 管理会計論 | 100点・60分・16問 | 問数増、配点調整 |
| 監査論・企業法 | 各100点・60分・20問 | 問数変更なし、試験時間調整 |
試験内容の進化:英語能力も問われる?
今後の公認会計士試験では、単なる会計・監査の知識だけでなく、国際化・デジタル化・サステナビリティといった新たな潮流への対応力も求められます。
まず注目すべきは、英語力の導入です。IFRS(国際財務報告基準)対応企業の増加や英文開示資料の活用が進む中で、実務レベルでも英文資料を正しく読み解く力が不可欠となってきています。そのため、短答式試験における英語読解の導入が検討されています。
また、サステナビリティ開示に関する出題も本格化します。2027年にはサステナビリティ情報の開示が法制化され、2028年からはその保証業務も求められるようになる見通しです。これを踏まえ、会計学・監査論などでESG情報に関する設問が加わる予定です。
さらに、IT・DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応力も重視されます。AI監査やリスクアセスメント、IT統制といった新たな業務領域に関する基礎知識を、今後の試験でも出題していく方向が示されています。
| 分野 | 新たに求められる能力・知識 | 出題への対応・変更点 | 導入予定時期 |
| 英語力(国際会計対応) | IFRS文書・英文開示資料の読解力 | 短答式試験に英語読解を含む問題の導入を検討中 | 検討段階(時期未定) |
| サステナビリティ情報 | サステナビリティ開示・保証に関する基礎知識 | 会計学・監査論に関連問題を出題予定 | 2027年〜(法制度導入時期に連動) |
| IT・DXリテラシー | IT統制、監査のデジタル化への理解 | 監査論に関連問題を追加(IT基準の改正にも対応) | 2025〜2027年を目安 |
| 選択科目の多様性確保 | 経営学一極集中からの脱却、多様な専門性の評価 | 経済学・統計学・民法など各科目の採点基準を見直し | 今後検討・段階的導入予定 |
選択科目の偏重是正も視野に
現在の選択科目における「経営学」一極集中(約97%)も、制度見直しの対象です。経済学・統計学・民法などの選択者が不利にならないよう、採点基準の調整や出題難易度の平準化が検討されています。将来的には、「好きな科目を選べる」という自由度を保ちつつ、どの科目を選んでも同等に合格可能な環境づくりが求められています。
| 項目 | 現状 | 今後の見直し・対応策 | 受験生への影響 |
| 選択科目の分布 | 経営学に約97%が集中 | 経営学への過度な偏重を是正 | 他科目(経済学・統計学・民法)選択者に公平な環境 |
| 採点基準の問題 | 経営学以外の科目は学力が適切に反映されない恐れ | 各科目の特性に応じた学力評価方法を検討 | 科目選択の自由度が高まる可能性 |
| 受験戦略への影響 | 無難な経営学選択が事実上の“固定戦略” | 他科目も視野に入れた多様な学習戦略が求められる | 得意分野を活かした戦略立案が可能になる |
受験生への影響と今後のスケジュール
本格的な制度変更は2027年度から段階的に実施される予定です。2025〜2026年度にかけては、新形式への移行準備期間として、受験環境や問題形式に大きな変化はありません。ただし、英語・サステナビリティ・IT系出題への布石は徐々に打たれていく可能性が高いため、早期にこれらの領域への対策を始めることが肝要です。
また、CBT方式の導入についても、今後数年間で試験環境がデジタルベースに移行していく可能性があります。これにより、ペーパーベースの記述式に慣れた世代の受験生にとっては、新たな試験形式への適応も課題となるでしょう。
| 年度(予定) | 試験制度の主な変更点 | 受験生への影響 |
| 2025年度 | ・出願方法の見直し検討 ・CBT方式の導入検討開始 |
・デジタル化に向けた環境変化に備える必要あり |
| 2027年度 | ・短答式の問題数 ・時間・配点の再設計反映開始 ・短答式合格率の引き上げ |
・計算問題中心の対策強化が必要 ・論文進出のチャンスが広がる |
| 2028~2030年度 | ・論文式試験の合格基準(52%→54%)へ段階的引き上げ ・採点体制の強化(専門委員・デジタル採点等) |
・論文の質的ハードルが上昇 ・表現力・論理力の訓練がより重要に |
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
公認会計士試験の“バランス調整”を徹底解説! -まとめ
今回の制度改革は、単なる出題形式の見直しではなく、公認会計士に求められる能力そのものの変化を反映したものであると言えます。受験生は、従来型の「暗記偏重型」の学習から脱却し、基礎力と応用力の両方をバランスよく育てる必要があります。
また、これまで軽視されがちだった英語やサステナビリティ、ITといった分野にも、今のうちから興味を持ち、能動的に情報を収集・学習する姿勢が求められます。過去問の分析はもちろん大切ですが、時代の変化を読み取り、変化に柔軟に適応できる“未来志向の学習”こそが、これからの合格のカギになるのです。
今後、公認会計士という資格は、「数字が強い人材」から、「変化に強く、価値を創造できる人材」へとシフトしていきます。これから試験を目指すすべての受験生にとって、今回の制度変更は“脅威”ではなく“チャンス”です。よりよい未来の自分のために、今、動き出しましょう。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)