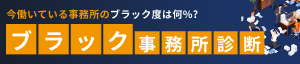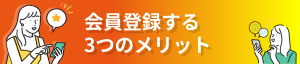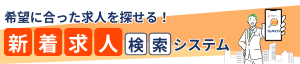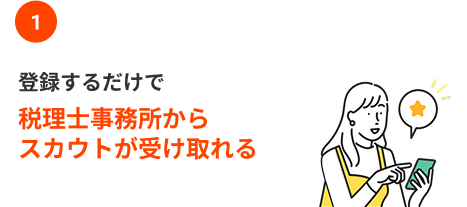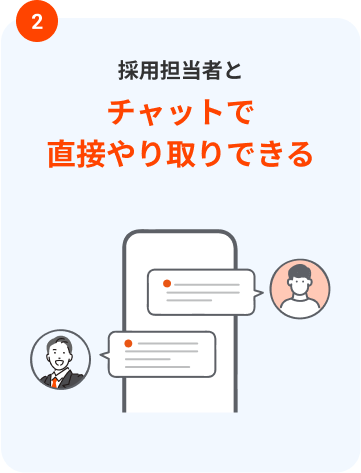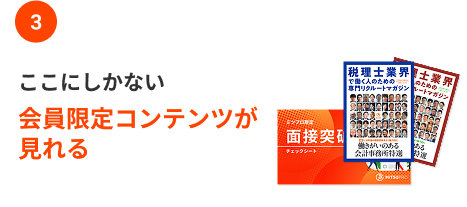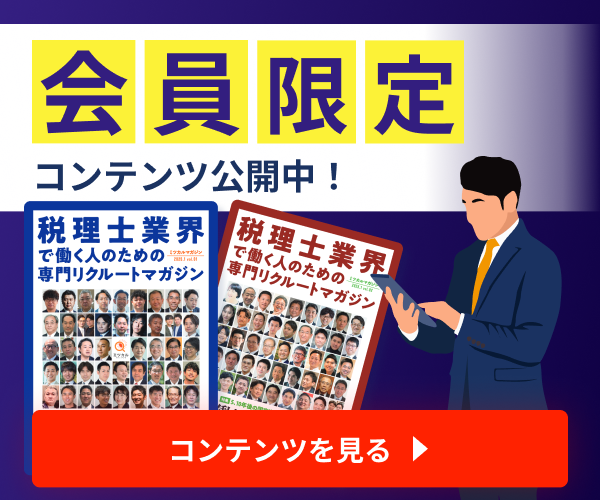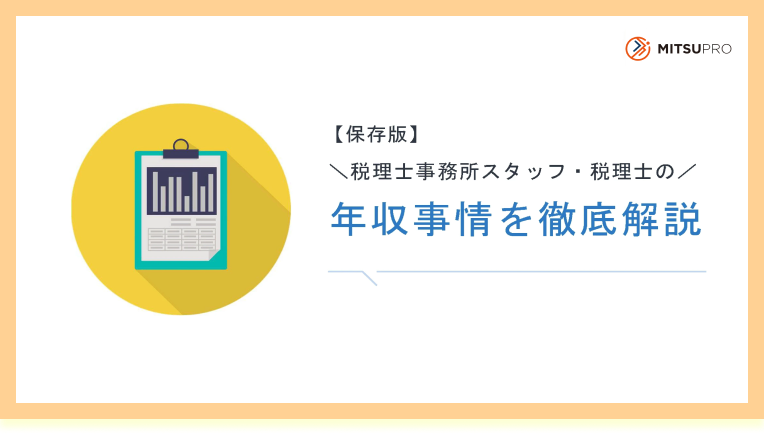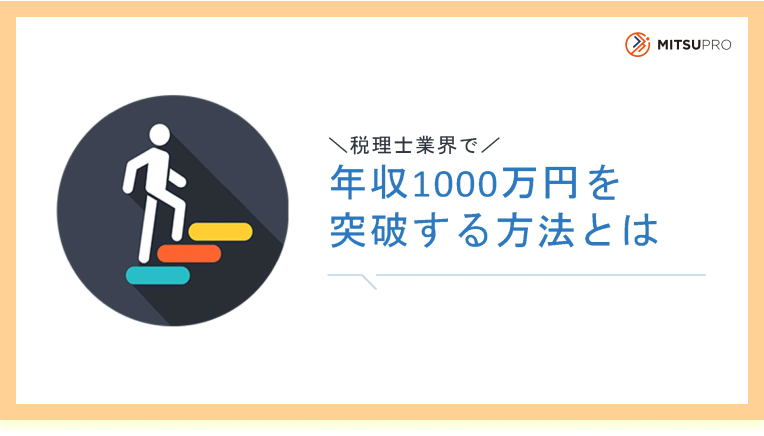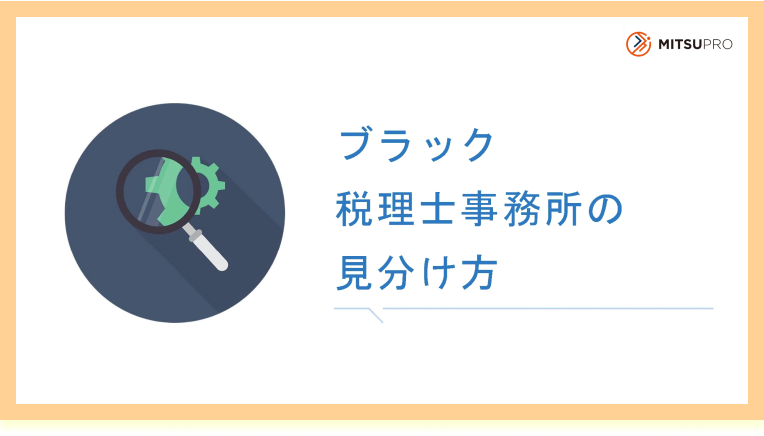INDEX
おすすめ記事
-

働きながら税理士試験に合格するには?無理なく仕事と勉強の両立を実現!
-
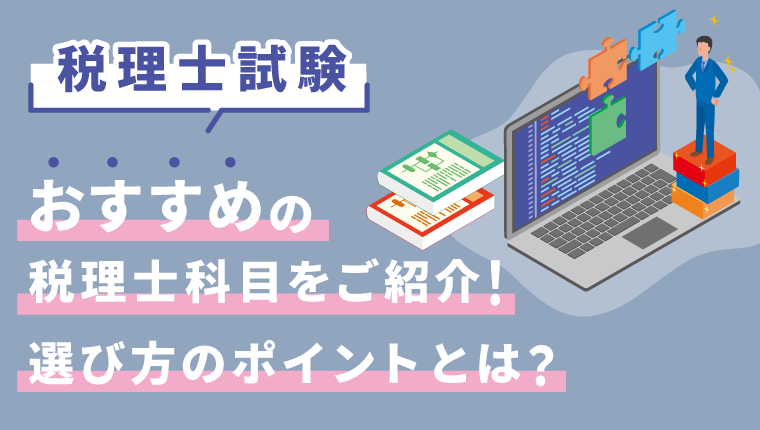
【税理士試験】おすすめの税理士科目をご紹介!選び方のポイントとは?
-

仮想通貨・暗号資産に強い税理士になるには
-
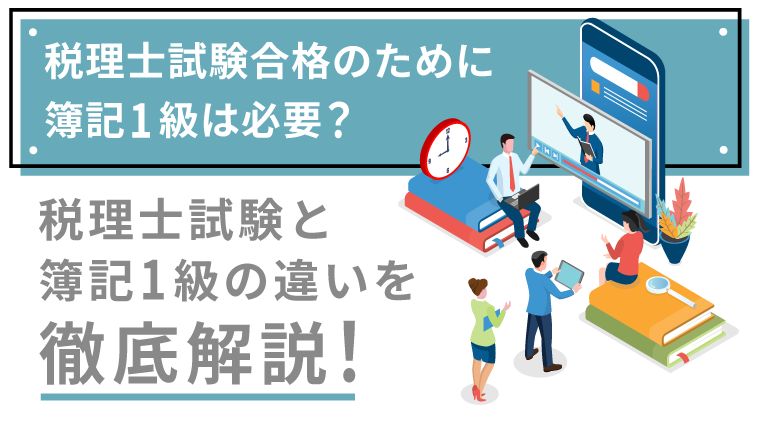
税理士試験合格のために簿記1級は必要?税理士試験と簿記1級の違いを徹底解説!
-
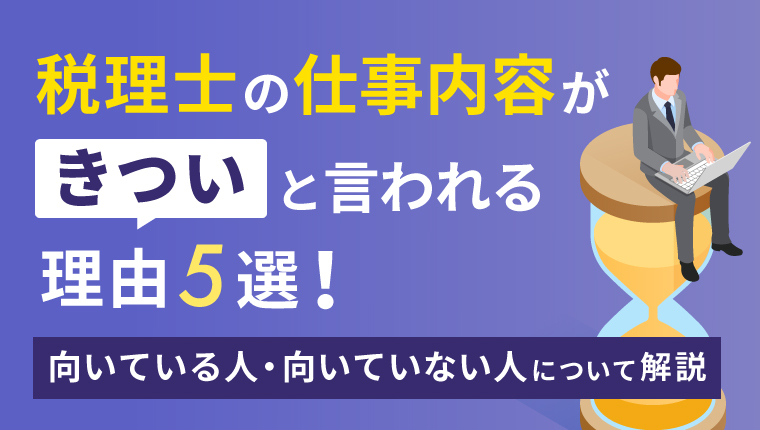
税理士の仕事内容がきついと言われる理由5選!向いている人・向いていない人について解説
「簿記1級はやめとけ」と言われる5つの理由と対処法


公開日:2025/08/21
最終更新日:2025/08/21
INDEX
簿記検定の中でも「最高峰」とされる日商簿記1級。就職や転職に役立つと考え、挑戦を検討する人も多い一方で、ネットやSNSでは「簿記1級はやめとけ」という声をよく目にします。なぜ、ここまで否定的な意見があるのでしょうか。
本記事では、その理由を5つに整理しつつ、それぞれに対する対処法を解説します。これを読むことで、「簿記1級は本当に自分に必要なのか」「どのように取り組めば挫折しないのか」が見えてくるはずです。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
簿記1級とは?
簿記1級とは、日本商工会議所(日商)が実施する 日商簿記検定の最上級レベル にあたる資格です。簿記検定には3級・2級・1級があり、1級はその中で最も難易度が高い試験と位置づけられています。
難易度
・合格率:およそ7〜12%前後
・必要学習時間:800〜1000時間以上
・受験者の多くは、2級合格者や経理職経験者であり、初学者がいきなり挑戦するのは極めて困難です>。
試験範囲
簿記1級の試験は以下の4科目で構成されています。
1.商業簿記
企業の会計処理を記録・整理する分野。連結会計、外貨建取引、金融商品など高度なテーマを扱う。
2.会計学
会計基準や理論を問う分野。企業会計原則や税効果会計、キャッシュ・フロー計算書などが出題対象。
3.工業簿記
製造業における原価計算や管理会計の基礎。2級の範囲を発展させ、標準原価計算・実際原価計算などを学ぶ。
4.原価計算
意思決定に役立つ管理会計の理論を扱う。直接原価計算、CVP分析、意思決定会計など。
この4科目すべてに合格点を取る必要があるため、範囲が広く対策が難しいのが特徴>です。
受験資格
特に受験資格の制限はなく、誰でも受験可能です。
ただし、公式には「2級程度の知識を有することが望ましい」とされており、実際の合格者も2級経験者が大多数>です。
試験日程
・年2回(6月・11月)実施。
・1度不合格になると、次の試験まで半年待つ必要があるため、計画的な学習が必須。
簿記1級の位置づけ
・実務的な即戦力資格というより、会計の理論と応用を体系的に理解している証明。
・経理・財務のプロフェッショナルとしての基礎固めとなる。
・公認会計士・税理士試験への登竜門としても知られている。
簿記1級はやめとけと言われる理由
「簿記1級はやめとけ」と言われる理由をまとめると、以下の様になります。
| 理由 | 詳細 | 対処法 |
| 1. 合格率が低すぎる | 合格率は7〜12%前後。試験は年2回のみで、不合格だと次は半年後。社会人にとってリスクが大きい。 |
・半年〜1年の長期計画を立てる ・「10%でもチャンスあり」と前向きに捉える ・過去問や模試で実力を客観的に測定 |
| 2. 学習範囲が広すぎる | 1級は「商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算」の4科目。深度も高く、専門書レベル。途中で挫折する人も多い。 |
・出題頻度の高いテーマに優先順位をつける ・教材は1シリーズに絞り混乱を避ける ・理解より演習重視で試験形式に慣れる |
| 3. 実務で使う機会が少ない | 経理実務では2級レベルで十分なことが多い。1級の知識を日常的に活かせる場は、大企業や監査法人など限定的。 |
・キャリア目標を明確にする ・税理士・会計士・診断士など上位資格と組み合わせる ・求人での「1級保持者歓迎」を狙う |
| 4. 勉強時間が膨大 | 必要勉強時間は800〜1000時間以上。2級の2〜3倍で、社会人には大きな負担。 |
・毎日の隙間時間を活用(朝30分・昼30分・夜1h) ・数か月の短期集中も有効 ・オンライン講座で効率学習 |
| 5. 挫折率が高い | SNSでも「途中でやめた」という声が多い。理由は合格率・範囲・時間負担の大きさ。特に社会人は途中で心が折れやすい。 |
・勉強仲間を作りモチベ維持 ・小さな目標を設定し達成感を積み重ねる ・資格取得の目的を紙に書き常に意識する |
それぞれ詳細を見ていきます。
簿記1級はやめとけと言われる理由1. 合格率が低すぎるから
簿記1級の合格率は例年 7〜12%前後 と非常に低く、難関資格といえます。さらに試験は年2回しか実施されないため、一度不合格になると次のチャンスまで半年待たなければなりません。勉強時間を確保できない社会人にとっては、挑戦自体がリスクに感じられ、「やめとけ」と言われがちです。
対処法
・長期計画を立てる
半年〜1年スパンで勉強計画を組み、短期合格を狙わない。
・合格率に惑わされない
「合格率10%」でも、しっかり対策すれば十分チャンスはある。
・模試で実力を測る
過去問や模試を繰り返し解くことで、自分の実力を客観的に把握できる。
「合格率が低い=不可能」ではなく、「対策が必要」だと捉えることが大切です。
簿記1級はやめとけと言われる理由2. 学習範囲が広すぎるから
簿記2級までが「商業簿記・工業簿記」を中心とするのに対し、1級は 会計学・商業簿記・工業簿記・原価計算 の4科目構成になります。しかも、それぞれの範囲が深く、専門書に近い内容を問われるのが特徴です。特に会計学では、企業会計基準や連結会計といった高度な知識が必要になります。
このため、「仕事をしながら勉強するのは大変すぎる」「途中で挫折する人が多い」という理由で「やめとけ」と言われます。
対処法
・優先順位をつける
全分野を完璧に仕上げるのは非現実的。出題頻度の高いテーマから攻略する。
・教材を厳選する
独学で複数の参考書に手を出すと混乱するため、テキストと問題集は1シリーズに絞る。
・アウトプット重視
理解よりも演習を中心に回すことで、試験形式に慣れる。
「広すぎる範囲を全部やる」のではなく、「試験に出る部分を重点的にやる」という発想の転換が合格への近道です。
簿記1級はやめとけと言われる理由3. 実務で直接使う機会が少ないから
「せっかく簿記1級を取っても、実務ではあまり役立たない」と言われることがあります。一般的な経理業務では簿記2級レベルの知識があれば十分な場合が多く、1級レベルの高度な会計処理を日常的に使うのは、大企業の経理や監査法人など限られた職場に限定されるからです。
そのため、「キャリアに直結しないのなら時間の無駄では?」と考える人もいます。
対処法
・キャリア目標を明確にする
経理のスペシャリストや公認会計士を目指すなら、1級は確実にプラス。
・周辺資格と組み合わせる
中小企業診断士、税理士、公認会計士などを目指す際の土台として活用できる。
・転職市場での強みを意識する
求人情報では「簿記1級保持者歓迎」と明記されるケースも少なくない。
実務に直結しない部分もある一方で、キャリアの選択肢を広げる効果があるのは事実です。
簿記1級はやめとけと言われる理由4. 勉強に膨大な時間がかかるから
簿記1級に必要な勉強時間は 600〜1000時間以上 と言われます。これは簿記2級の2〜3倍以上のボリュームで、社会人にとっては相当な負担です。仕事や家庭と両立できず、途中で投げ出す人が多いのも現実です。
この「時間的コスト」が、挑戦を躊躇させる大きな理由となっています。
対処法
・毎日のルーティンに組み込む
朝30分、昼休憩30分、夜1時間など、隙間時間を積み重ねる。
・短期集中も検討する
仕事を調整し、数か月間は簿記1級に全力投球する戦略も有効。
・オンライン講座を活用
独学に比べ効率が良く、必要なポイントを絞って学習できる。
「時間がかかる」のは事実ですが、やり方次第で効率化は可能です。
簿記1級はやめとけと言われる理由5. 挫折率が高いから
SNSや口コミでよく見るのが「途中でやめた」という声です。理由は前述の通り、合格率の低さ・範囲の広さ・時間的コストの大きさです。特に社会人は忙しいため、途中で心が折れてしまう人が少なくありません。結果的に「挑戦しても挫折するだけだから、やめとけ」と言われてしまいます。
対処法
・仲間を作る
SNSや勉強会で仲間を作ると、モチベーションを維持しやすい。
・小さな目標を設定する
「1か月でこの章を終える」「1週間で10問解く」など、達成感を積み重ねる。
・資格取得の目的を紙に書く
「なぜ簿記1級を取るのか」を常に意識すると挫折しにくい。
モチベーション管理さえできれば、挫折のリスクは大きく下げられます。
簿記1級に挑戦するメリット
ここまで「やめとけ」と言われる理由を解説しましたが、それでも簿記1級に挑戦する価値は十分にあります。特に、以下の3つの点で大きなメリットがあります。
メリット全体像
| メリット | 内容 | 活かせる場面 |
| 知識の深化 | 経理・会計の専門知識が圧倒的に深まる | 実務力強化、経理のリーダー職 |
| キャリアの広がり | 大手企業や会計事務所への転職に有利 | 求人応募、昇進、部署異動 |
| 上位資格への土台 | 税理士・公認会計士へのステップアップ | 資格試験対策、キャリアチェンジ |
1. 経理・会計の知識が圧倒的に深まる
・簿記2級まででは学ばない「連結会計」「企業会計基準」「税効果会計」などを体系的に習得できる。
・実務では出てこない高度な論点も扱うため、経理部門のスペシャリストとしての基盤を築ける。
・財務諸表を「作れる」だけでなく、「分析できる」レベルまで視野が広がる。
結果:単なる事務処理担当ではなく、経営に助言できる存在へと成長可能。
2. 大手企業や会計事務所への転職に有利
・求人票で「簿記1級保持者歓迎」と記載されるケースが増えている。
・特に上場企業や監査対応が必要な企業では、1級保持者の評価が高い。
・採用担当者からすると「簿記1級=会計の専門家予備軍」として安心感がある。
・実際に「2級では応募可能止まり、1級で書類通過」という事例も少なくない。
結果:キャリアの選択肢が広がり、年収アップやキャリアチェンジに直結。
3. 税理士・公認会計士など上位資格へのステップになる
・税理士試験(簿記論・財務諸表論)や公認会計士試験の基礎範囲と大きく重なる。
・簿記1級を合格した人は、税理士科目や会計士試験にスムーズに移行できる。
・「会計の基礎力」があることで、他の資格学習が効率化する。
・上位資格を取らなくても、「1級まで取った」という学習経験自体が評価される。
結果:将来のキャリアの可能性を広げ、ステップアップに直結。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
簿記1級が「やめとけ」と言われるのは、以下の5つの理由からです。
1.合格率が低すぎる
2.学習範囲が広すぎる
3.実務で直接使う機会が少ない
4.勉強に膨大な時間がかかる
5.挫折率が高い
確かにハードルは高い資格ですが、それぞれの理由には対処法があります。キャリアの方向性を明確にし、学習計画を工夫すれば、合格は十分に可能です。
簿記1級を取るべきか迷っている方は、「やめとけ」という言葉を鵜呑みにするのではなく、自分の目標やライフスタイルに合わせて判断してください。挑戦する価値は、あなた自身の将来像によって決まるのです。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)