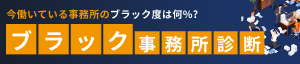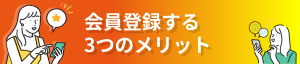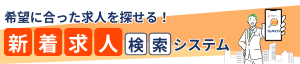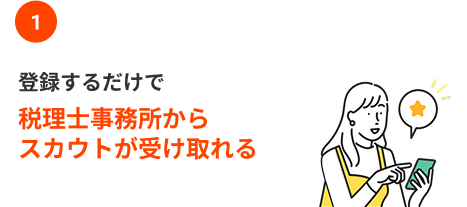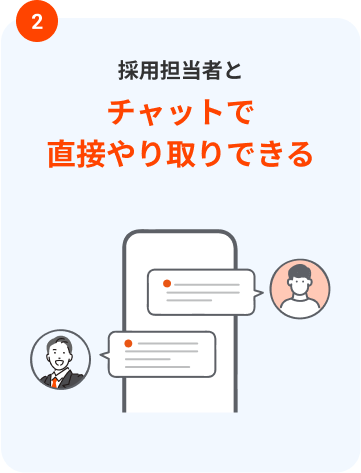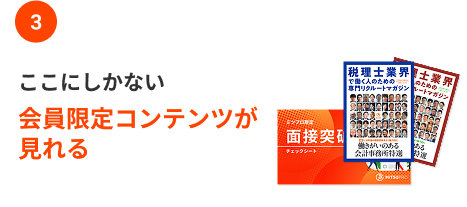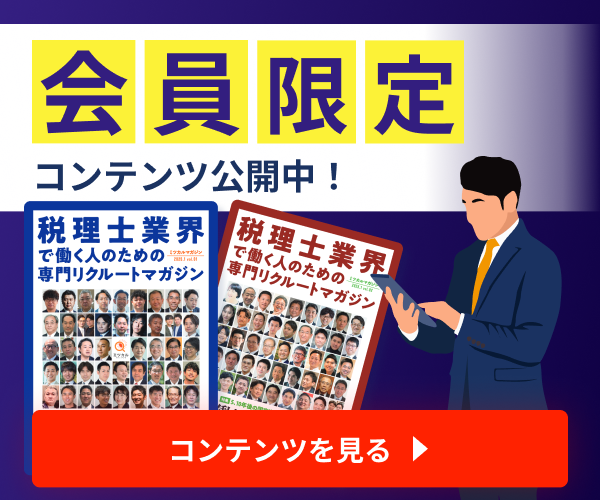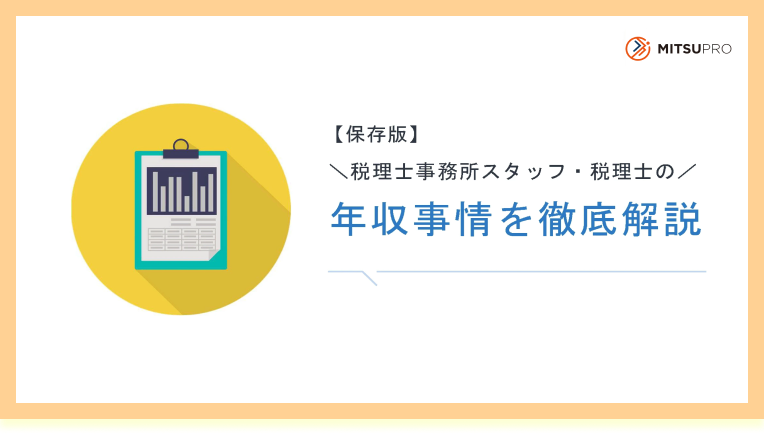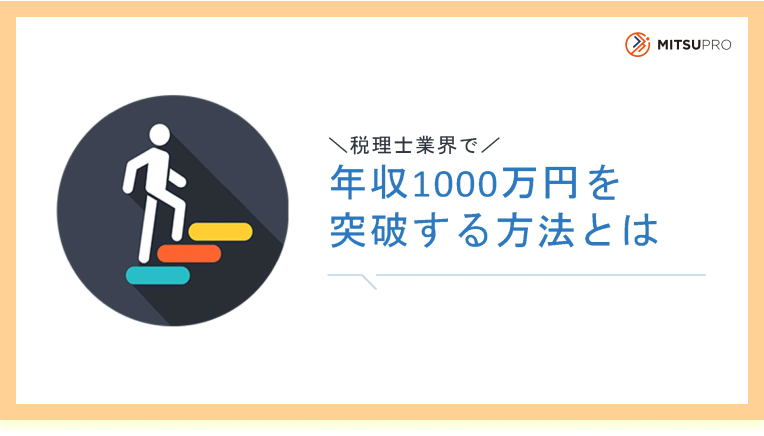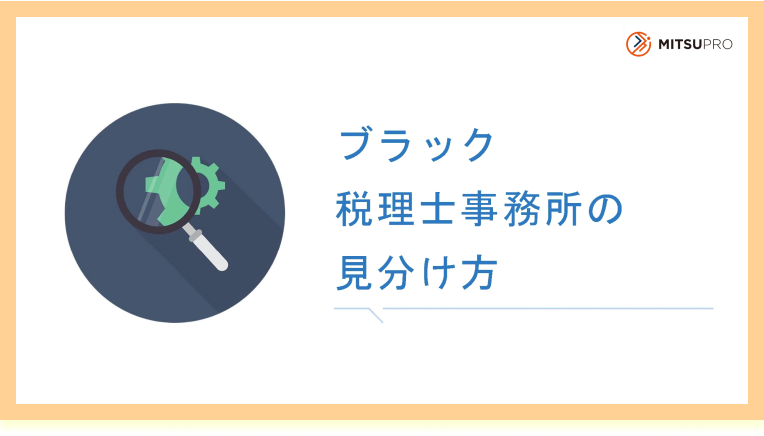INDEX
おすすめ記事
-
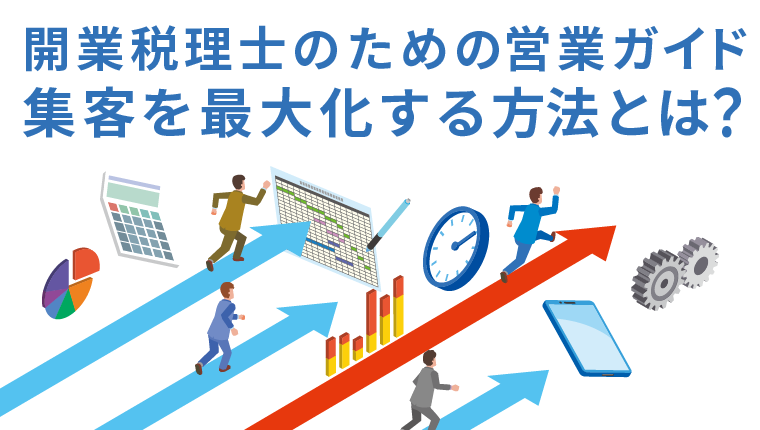
開業税理士のための営業ガイド|集客を最大化する方法とは?
-
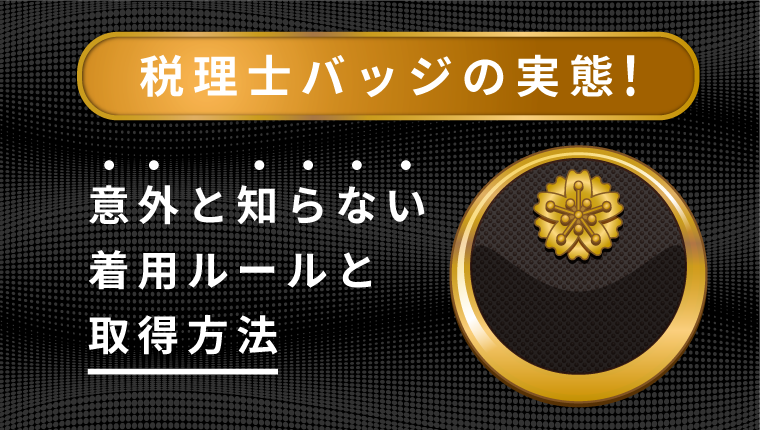
税理士バッジの実態!意外と知らない着用ルールと取得方法
-

税理士試験の国税徴収法:合格への最短ルート【令和7年(2025年)最新版】
-
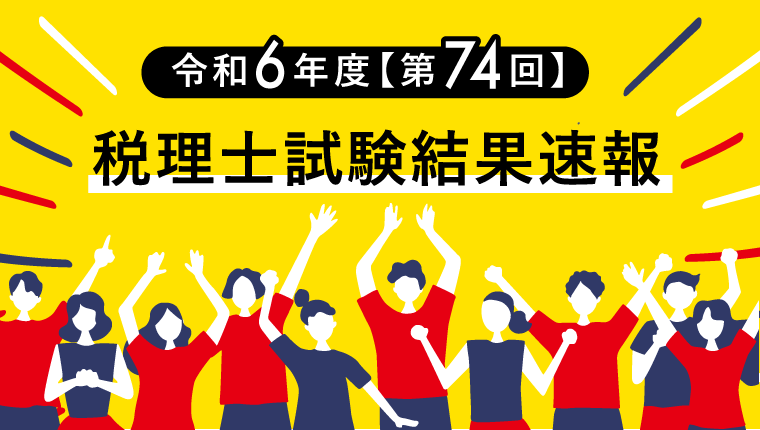
令和6年度(第74回)税理士試験結果速報
-
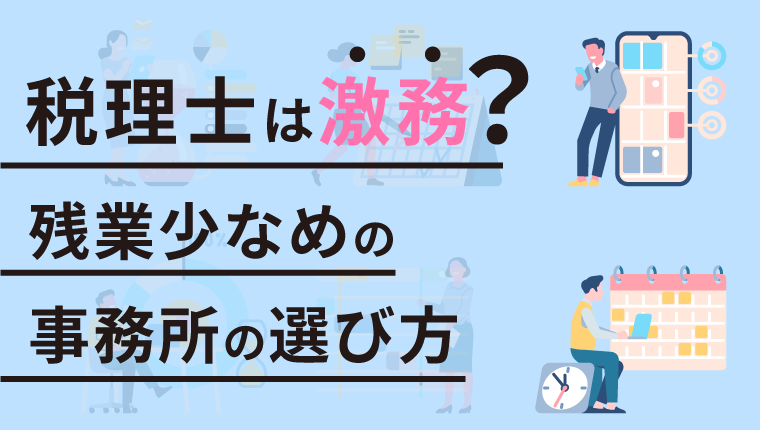
税理士は激務?残業少なめの事務所の選び方
【保存版】税理士試験の科目はどう選ぶ?戦略的な選び方とおすすめ組み合わせ


公開日:2025/08/21
最終更新日:2025/08/21
INDEX
税理士試験は、会計科目2科目+税法科目3科目の合計5科目に合格することで資格取得ができます。しかし、すべての科目に一発で合格するのは非常に難しく、合格までに平均5〜10年かかる人も少なくありません。そのため「どの科目から受験するか」「どんな順番で進めるか」は、合格までのスピードを大きく左右します。
本記事では、これから受験を考えている方に向けて、戦略的な科目の選び方とおすすめの組み合わせを徹底解説します。
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
税理士試験の基本構成とは?
税理士試験は、会計科目と税法科目から構成されています。まず会計科目としては「簿記論」と「財務諸表論」の2科目が必須です。これに加えて、税法科目の中から3科目を選択する必要があります。税法科目には「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法」をはじめ、「酒税法」「固定資産税」「住民税」「事業税」「国税徴収法」など複数の選択肢があります。その中でも、実務での需要や出題頻度を踏まえて、多くの受験生は「法人税法」「所得税法」「相続税法」「消費税法」のいずれかを選択するケースが一般的です。
科目選びの基本方針
税理士試験の科目を選ぶ際には、やみくもに人気科目や難易度だけで判断するのではなく、自分の学習スタイルや将来のキャリアを踏まえて戦略的に選ぶことが重要です。ここでは、受験生が意識すべき4つのポイントを解説します。
1. 合格のしやすさ(ボリューム・出題傾向)
科目ごとに出題範囲の広さや難易度は大きく異なります。たとえば、範囲が比較的コンパクトな「消費税法」や「酒税法」は、短期合格を狙いやすい科目として知られています。一方で「法人税法」や「所得税法」は出題範囲が膨大で理論問題も多く、長期間の学習を覚悟する必要があります。
つまり、まずは合格しやすい科目で科目合格を積み重ねてモチベーションを維持するのか、それとも時間をかけて王道科目に挑戦するのかを明確にすることが大切です。
2. 将来のキャリアとの相性
科目選択は、将来どのような税理士になりたいかによっても変わってきます。たとえば、相続や資産承継分野で強みを持ちたいなら「相続税法」を選ぶのが王道です。法人をメインの顧客としたい場合は「法人税法」が必須とも言える存在です。逆に、個人事業主やフリーランスのサポートを重視するなら「所得税法」が役立ちます。
単に「合格しやすい」だけでなく、将来の専門性や仕事の方向性を意識した科目選択をすると、実務に直結しやすくキャリアの武器になります。
3. 学習のバランス
1年間で複数科目を受験する場合、「重い科目」と「軽めの科目」を組み合わせるのが鉄則です。たとえば「法人税法」と「消費税法」など、ボリュームの多い科目と比較的短期合格が狙える科目を同時に勉強すると、学習負担のバランスがとりやすくなります。
逆に「法人税法+所得税法」のように重い科目同士を一度に挑戦すると、学習時間が圧倒的に足りず、両方とも中途半端になってしまう危険があります。
4. 自分の得意分野
最後に忘れてはいけないのが、自分自身の得意・不得意を踏まえることです。計算スピードが得意な人は簿記論や消費税法の計算分野で有利に進められます。一方で、暗記や理論的な整理が得意な人は、財務諸表論や法人税法の理論分野で力を発揮できます。
自分が「暗記型か」「理解型か」「計算型か」を見極めて、得意分野を活かせる科目を選ぶと、学習効率が格段に上がります。
科目ごとの特徴と難易度
税理士試験では、必須科目と選択科目の特徴や難易度が大きく異なります。自分の得意分野や将来のキャリアを意識しながら、どの科目を選ぶかを戦略的に判断することが大切です。ここでは代表的な科目について、それぞれの特徴・難易度・学習のポイントを解説します。
科目別の特徴・難易度一覧
| 科目 | 特徴 | 難易度 | 学習のポイント |
| 簿記論(必須) | 商業簿記・工業簿記を中心とした計算問題 | ★★★★★ | 受験生全員が受ける科目。合格率は10%前後と低く、スピードと正確性が重要。基礎固めが合否を左右する。 |
| 財務諸表論(必須) | 計算と理論のハイブリッド科目 | ★★★★☆ | 理論暗記が中心だが計算問題も出題。簿記論と同時学習で理解が深まる。 |
| 法人税法 | 税法の中で最も範囲が広くボリュームが大きい | ★★★★★ | 学習量が膨大で合格までに時間がかかるが、キャリア上の価値が高い。企業税務に携わりたい人は必須級。 |
| 所得税法 | 個人所得の総合課税・分離課税を中心に出題 | ★★★★☆ | 理論量が多く、理解力と暗記力の両方が必要。個人事業主や資産税に強い税理士を目指す人に最適。 |
| 相続税法 | 相続財産の評価や課税を扱う事例計算が中心 | ★★★☆☆ | 出題範囲は広いが、法人税や所得税ほどではない。資産税に強みを持ちたい人におすすめ。 |
| 消費税法 | 範囲が比較的コンパクト | ★★☆☆☆ | 短期合格が狙いやすく、法人税や相続税と並行受験する人が多い。暗記と計算をバランス良くこなせる科目。 |
| 酒税法・国税徴収法など(マイナー科目) | 出題範囲が小さく短期集中で学習可能 | ★☆☆☆☆ | 合格科目を早めに稼ぎたい人に有効。ただし実務での活用度は低い点に注意。 |
補足解説
・簿記論・財務諸表論は全員が必須で受験するため、どの受験生も避けられません。特に簿記論はスピードと正確性が求められ、財務諸表論は理論暗記力も試されます。この2科目を同時に学ぶことで、相互に理解を深めやすくなります。
・法人税法・所得税法は「重い税法科目」の代表格です。学習量が膨大で難易度も高いですが、税理士としてのキャリアを築くうえで欠かせない存在です。
・相続税法は、将来的に資産税案件を得意分野にしたい人には必須級。出題範囲は広いものの、法人税や所得税に比べれば取り組みやすい側面もあります。
・消費税法は範囲が比較的コンパクトで、短期間で合格できる可能性があるため、戦略的に選ばれるケースが多い科目です。
・酒税法や国税徴収法などのマイナー科目は、出題範囲が狭く短期合格を狙えるため、合格科目を稼ぎたいときに有効です。ただし実務で使う場面は少ないため、キャリアを重視する人は慎重に選ぶ必要があります。
戦略的な科目の組み合わせ
税理士試験を効率的に突破するためには、重い科目(学習量が膨大で難易度が高い科目)と軽めの科目(範囲がコンパクトで短期合格が狙える科目)をバランス良く組み合わせることが重要です。すべてを重い科目で固めてしまうと学習負担が大きすぎて挫折しやすくなり、逆に軽めの科目ばかり選ぶと最終的に難関科目が残って長期化する危険があります。
ここでは王道の組み合わせパターンと、受験生の志向に合わせた応用パターンを紹介します。
王道の進め方(3年計画モデル)
| 年度 | 科目の組み合わせ | 戦略のポイント |
| 1年目 | 簿記論+財務諸表論(必須セット) | すべての基礎となる会計力を養成。計算力と理論の基礎を固め、以後の税法科目学習の土台を作る。 |
| 2年目 | 法人税法+消費税法 | 税法の王道である法人税法に挑戦しつつ、比較的軽めの消費税法で合格可能性を確保。バランス重視。 |
| 3年目 | 相続税法または事業税 | キャリアの方向性に合わせて最後の1科目を選択。 |
この3年間モデルは、多くの合格者が採用している「定番の王道パターン」で、合格までの流れをスムーズに描ける組み合わせです。
その他の組み合わせ例
受験生の学習スタイルやキャリア志向によっては、以下のようなパターンも有効です。
| タイプ | 科目の組み合わせ | 特徴・向いている人 |
| 短期集中型 | 消費税法+酒税法 | 出題範囲が狭い科目を同時受験し、短期で「合格済み科目」を稼ぎたい人向け。ただし最終的に重い科目が残らないよう注意。 |
| 資産税特化型 | 相続税法+固定資産税 | 資産税分野に特化し、相続案件や不動産関連の顧客をターゲットにしたい人向け。将来の差別化にもつながる。 |
| 法人特化型 | 法人税法+消費税法+事業税 | 法人クライアントをメインに考えている人向け。法人税と事業税の学習内容に関連があり、効率的に知識を活用できる。 |
| 王道バランス型 | 法人税法+相続税法+消費税法 | 実務対応の幅が広がり、キャリア的にも安定。バランス良く科目を配置したい人におすすめ。 |
組み合わせを考えるときの注意点
1.重い科目と軽い科目を必ず組み合わせる
◦法人税法+所得税法のような重い科目同士は避ける
◦合格実績を積み上げながらモチベーション維持を意識
2.キャリアに直結する科目を残さない
◦「最後に法人税法だけ残った」というケースは非常に大変
◦軽めの科目で先に合格実績を作りつつ、メインの重い科目も計画的に配置
3.受験可能な時間を逆算する
◦社会人受験生は学習時間に限りがあるため、まずは短期合格が狙える科目を取り入れる
◦専念できる時期に法人税法や所得税法などの重い科目を配置すると効率的
よくある失敗と注意点
税理士試験は長期戦になりやすいため、科目選びを誤ると途中で挫折したり、合格までの期間が大幅に延びてしまうケースが少なくありません。ここでは受験生が陥りやすい代表的な失敗と、その回避策を解説します。
1. 重い科目ばかり選んでしまう
例:法人税法+所得税法+相続税法
これらは出題範囲が非常に広く、理論暗記・事例計算ともにボリュームが膨大です。学習時間を確保できる人であっても、複数科目を同時進行すると理解が浅くなり、結局どの科目も得点が伸びないまま試験日を迎えてしまうことがあります。
回避策:
・「重い科目+軽めの科目」を基本とする(例:法人税法+消費税法)
・学習初期はまず会計科目を固め、その後に重い税法科目に移行する
・合格計画を3〜5年スパンで立て、無理のない科目配分にする
2. 興味だけで選んでしまう
例:マイナー科目(酒税法や国税徴収法)を先に選択
マイナー科目は範囲が狭く短期で合格しやすいため、早く合格実績を作りたい受験生には魅力的です。しかし興味だけで先に選んでしまうと、最終的に「法人税法や所得税法といった重い科目」が後回しになり、学習の後半で負担が一気にのしかかります。これにより、最後に一番大変な科目が残ってしまい合格までの年数が長期化するケースがよくあります。
回避策:
・軽い科目を選ぶ際も「最終的に必要な重い科目をいつ取るか」を同時に計画しておく
・興味だけでなく、将来のキャリアや実務に役立つかどうかも基準にする
・「まずは合格を稼ぐ」という戦略は有効だが、残りの科目が偏らないように注意する
3. 計画を立てずに科目を増やす
例:1年で3科目以上を受験する
「早く合格したい」という思いから、計画を立てずに科目数を増やす受験生も少なくありません。しかし、税理士試験は1科目あたりの学習量が非常に多いため、3科目以上を同時に受験するのはリスクが高い戦略です。特に初学者の場合、どの科目も中途半端な仕上がりとなり、全落ちしてしまう危険性があります。
回避策:
・初年度は2科目以内に抑え、まずは「簿記論+財務諸表論」で基礎を固める
・受験経験を積んでから「重めの税法+軽めの税法」の2科目に挑戦する
・本試験までに合格レベルまで仕上げられる学習時間を逆算し、受験科目数を決定する
働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。
⇒無料で会員登録して雑誌を見る
まとめ
税理士試験は「どの科目をどんな順番で選ぶか」で合格スピードが大きく変わります。
・まずは簿記論+財務諸表論で基礎固め
・次に法人税法+軽めの科目(消費税法など)
・最後にキャリア志向に合わせた科目(相続税法や所得税法)
この流れが王道であり、最も多くの合格者が実践しているパターンです。
効率的に合格を目指すなら、「重い科目と軽い科目のバランス」を意識して、自分の得意分野や将来のキャリアに合った戦略を立てましょう。
この記事がお役に立てば幸いです。

平川 文菜(ねこころ)